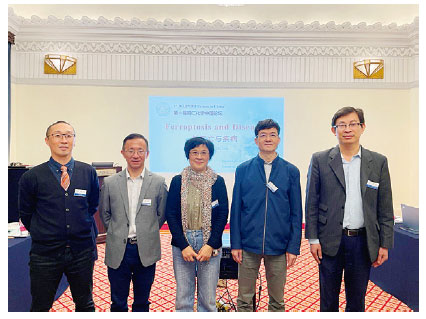開催後記
第34回フォーラム・イン・ドージン
「脳の未来への挑戦 新薬革命と神経変成疾患を克服する新時代
~夢か現実か、議論の舞台裏~」
第1 回 Dojindo Forum in China
「Ferroptosis and Diseases」
第34 回フォーラム・イン・ドージン
2023年12月にアルツハイマー病治療薬である「レカネマブ」が発売され、また今年に入り「ドナネマブ」の認可への動きが出てきており、アルツハイマー病の治療に新たな光が差し込んできた。今回第34回目を迎えるフォーラム・イン・ドージンは、「脳の未来への挑戦 新薬革命と神経変性疾患を克服する新時代~夢か現実か、議論の舞台裏~」というテーマで11月15日に開催した。神経変性疾患研究にフォーカスし、この研究領域でトップランナーである7名の先生方を熊本に迎えご講演いただいた。講演はweb配信され、300名を超える聴講者を数え、大変盛会であった。座長は例年通り、熊本大学 富澤一仁教授、三隅将吾教授に務めていただいた。以下講演タイトルと演者の先生方を記す(講演プログラム順)。
「アルツハイマー病病態形成とグリアネットワーク」
名古屋市立大学 齊藤 貴志教授
「TARDBPエキシトロンスプライシングを標的とした筋萎縮性側索硬化症に対するアンチセンス核酸治療」
新潟大学 須貝 章弘講師
「α- シヌクレインシードの検出とα- シヌクレイノパチー病態解明への期待」
順天堂大学 奥住 文美准教授
「トランスサイレチンアミロイドーシスの病態解明と治療法の進歩」
熊本大学 三隅 洋平准教授
「オートファジー促進によるパーキンソン病に対する治療戦略」
筑波大学 斉木 臣二教授
「リピート伸長変異による神経変性疾患:明らかになる遺伝学と新規分子病態」
近畿大学 藤野 雄三研究員
「アルツハイマー病治療薬開発の現状と展望」
東京大学 岩坪 威教授
今回はこれまでとは違い(これまでは基礎研究をテーマとしてきた)より臨床に近いテーマを選定したが、活発な討議がなされ神経変性疾患治療に対する関心の高さがうかがえた。アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患は、昔は治らない病気と思われていたが、抗体医薬等治療薬の開発が飛躍的に進み、今や治療できるところまで来ている。これらの疾患の治癒が夢から現実になることを切に願う。
第1回Dojindo Forum in China
日本では1990 年よりフォーラム・イン・ドージンを開催し今年第34 回目を迎える。「熊本から世界へ」を合言葉にその当時の先端の研究トピックスを発信してきた。中国での最新のトピックスを世界へ発信する目的で、11月1日に上海にあるOkura Garden Hotelに中国国内外で活躍されている5名の先生をお招きし、第1回Dojindo Forum in Chinaを開催した。講演は日本で開催しているフォーラムと同様、オンライン形式により中国全土に配信された。
第1回目は、「Ferroptosis and Diseases」というタイトルで、今中国で一番ホットな研究テーマであるフェロトーシス研究にフォーカスを当てた。南開大学のQuan Chen教授にオーガナイザーをお引き受けいただき(講演演題:Molecular Regulation of Ferroptosis and Its Implication in Fighting Cancers and Other Diseases)、アメリカからは、Memorial Sloan Kettering Cancer Center のXuejun Jiang教授(講演演題:Ferroptosis, Mechanisms and Roll in Disease)、日本からは岐阜薬科大学の平山祐准教授(講演演題:Fluorescent Probes for Imaging Fe(II) and Hem in Living Cells)、そして中国国内から南京大学のKuanyu Li教授(講演演題:Physiology and Pathology of Cellular and Mitochondrial Iron Metabolism)、同済大学のPing Wang教授(講演演題:Distal Cholesterol Biosynthesis Regulates Ferroptosis)をお迎えし、盛況のうちにフォーラムを終えることができた。
今回のテーマであるフェロトーシスは非アポトーシス細胞死の中の一つに分類され、リン脂質の過酸化によって駆動される鉄依存的な細胞死様式である。先生方の講演では、フェロトーシスが癌、虚血性心疾患や臓器虚血再灌流障害などの疾患の治療に重要な役割を果たすことが示された。フェロトーシスの制御メカニズムの研究が今後重要な臨床応用へつながっていく可能性が期待される。
聴講者は5,500名を超え、中国でのフェロトーシス研究の熱さを感じた。今やフェロトーシス研究は中国が世界をリードしている感が強い。第2回目のフォーラム開催に向け、中国から世界に情報発信できるテーマの選定を今から進めていきたい。
(石山 宗孝)