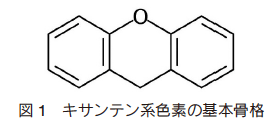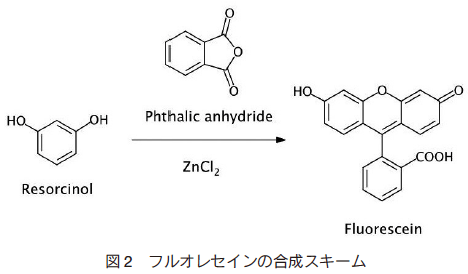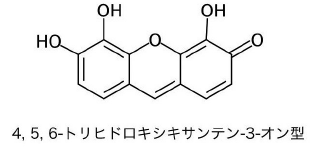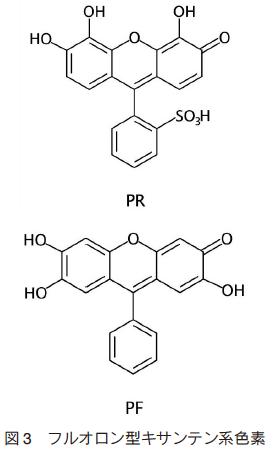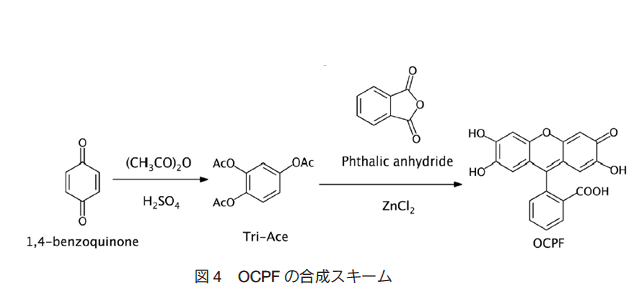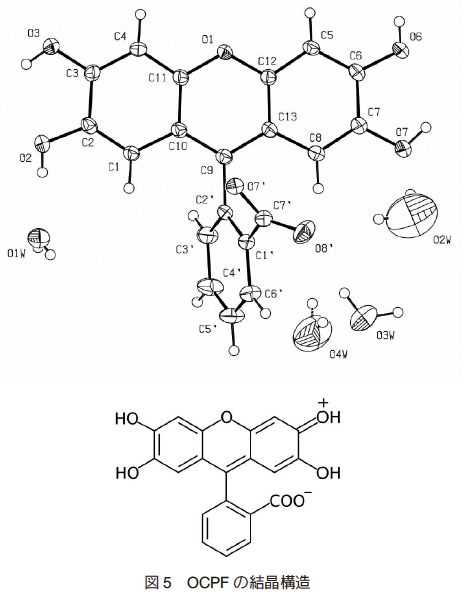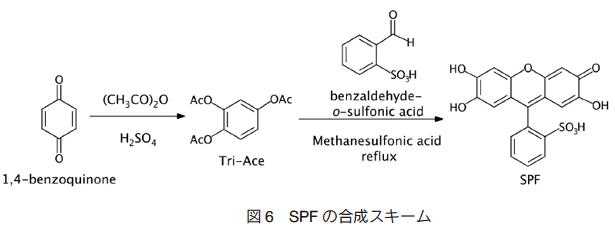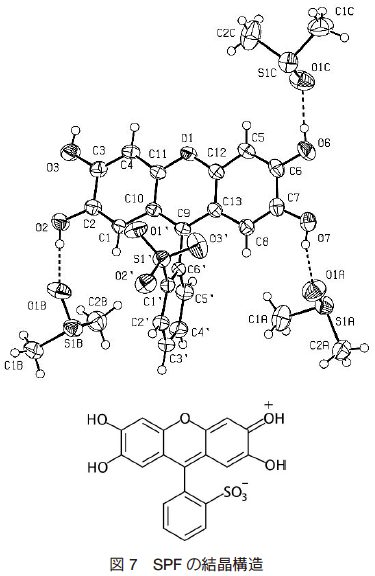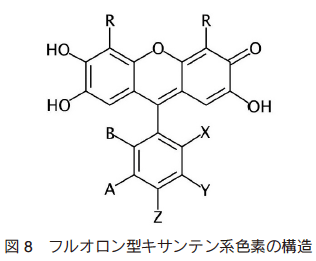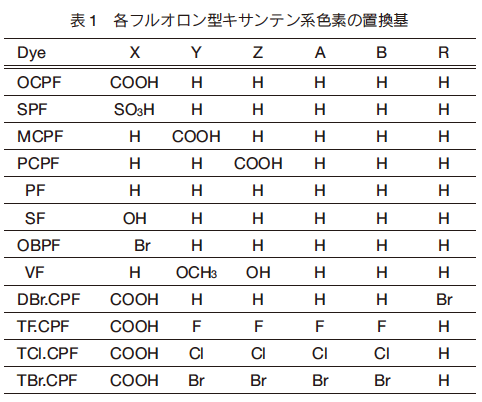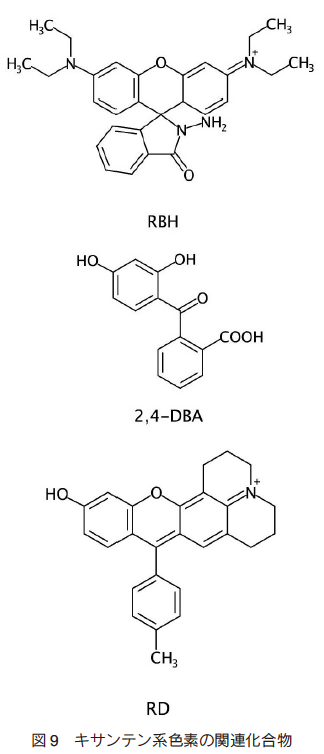�L���[�g����Ƃ��Ẵt���I�����^�L�T���e���n�F�f�̍����Ƌz�����x���͂ւ̉��p
Synthesis of the fluorone-type xanthene dyes as a chelating reagent and application to spectrophotometric analysis
 |
���c�@�F�� ����ȑ�w���_���� ���M�����w�@ �T�G����� �O�����[�����e���w�Z |
Abstract
�@We synthesized 2, 6, 7 -trihydroxy xanthene-3-one type (fluorone type) xanthene dyes having excellent properties as a chelating reagent, and developed novel spectrophotometric methods of various metal ions, pharmaceuticals, biogenic constituents by incorporating analytical creativity such as the ternary complex formation reaction and/or the competitive complexation reaction in surfactant micellar media. Further developed methods were applied to a variety of real samples. In addition, some reaction mechanisms in employed analytical conditions were clarified by determined the binding parameters, thermodynamic parameters and so on. I introduce the outline in the present review.
1�D �͂��߂�
�@���͉��w�́A���i���́A�����́A�H�i���́A�Տ����͓������镪��ɔėp����Ă���K�v�s���Ȋ�ՋZ�p�̂ЂƂł���A���̕��͉��w�̔��W�ɂ͕��͋@��̔��W�ɑ�\�����n�[�h�ʂł̐i���A���͎���Ƃ��̗��p�@�̊J���ɑ�\�����\�t�g�ʂł̐i�W�����̗��ւł���B����A�����͖@�̑�\�ł���z�����x�@�́A�ȕցA�v���A�Č����ɗD�ꂽ���@�Ƃ��ċ������邢�͔�����A����ɂ͈��i�C���̐����Ȃǂ̕��͂ɔėp�����ȂǁA���p�͈͂͋ɂ߂čL�����A���̔��ʁA�ړI�ɂ���Ă͊��x�A�I�𐫂ɂ����Ă��s�\���ȏꍇ������A���̑��̋@�핪�͂̒������i�����W�ɂ��A�V�������������̒T����V�����L�@����̊J�����܂߁A���̊��p�ʂɂ�����V�����\�����J�悤�Ƃ��錤���͋ߔN�]�芈���ɂ͍s���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�������Ȃ���A�z�����x�@�́A����l�������z���W�� �iε�j�ň�`�I�ɐ����ł���A�����ȋ@���p���ĊȈՂȑ���ŐM��������f�[�^����r�I�����x�ɓ�����Ȃǂ̓�����L���A�n�[�h�ʂł́A�i1�j �z���x 0.001 ���Č����悭����ł��镪�����x�v���J�����ꂽ���ƁA�\�t�g�ʂł́A�i2�j�������̐��������Ȃǂ̐V�������@�̊J�����p���\�Ȃ��ƁA�i3�j�����x�A���I��I�ȐV�K�L�@����̊J�����p���\�Ȃ��ƁA�܂��A�i4�j�t���[�C���W�F�N�V�����@�iFIA�j�⎩�����͂ɓK�p����₷���A�i5�j���茋�ʂ�ڎ��Ŋm�F�ł���A�i6�j���w���t�_�I�ɍl�@���₷���A�i7�j���ɑ��đΏ����₷���A �i8�j�X�y�V�G�[�V�������͂��\�ł���ȂǁA�ɂ߂đ��l�ȓ�����L����D�ꂽ���͖@�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ�1-3�j �B����ɁA�ŋ߁A�Տ����w����Ȃǂł́A�����e��ƃZ�������ˑ����̃E�F��������A�������̂��ɋz���x����ł���}�C�N���v���[�g�v���@ 4�C5�j ��i�m�e�N�m���W�[�����p���������E�v���Z�p�ł���}�C�N���`�b�v�v���@ 6-9�j �����������W���Ă��Ă���B����ɁA�ȕ��A�v�����A�o�ϐ��Ȃǂ̖ʂŗD�ꂽ�X�|�b�g�e�X�g�A�������@�Ȃǂ̖ڎ����� 10�C11�j���������o�ꂵ�Ă���A�z�����x�@�̎���͈͂��L�����Ă���B
2�D�z�����x�@�̊��x�ƗL�@����
�@�@�@�@�@�z�����x�@�̊��x ε �́A Braude �̌o���� 12) ε ��κ Pa�i κ�F1020 ���x�̒萔�AP�F�J�ڊm���Aa�F��F���w��̋z���f�ʐ�)���A a �� P �Ɉˑ�����B�]���āA�����x���͖@��ݒ肷�邽�߂ɂ́A���� a ���\�Ȍ���傫�����邩�AP �̑J�ڊm�������� π�|π���J�ڂ��N�����₷���L�@����𗘗p���邱�Ƃ��ɂ߂ėL���ł���B a ��傫������\�t�g�ʂł̈�̕���Ƃ��āA�O�����́i�O�������́j1�C 3�C 13-17�j�̗��p�A���Ȃ킿�����C�I���A�������ܕ��тɗL�@����̎O�҂ɂ����̂������锽���n�̗��p�����ɗL���ł��邱�Ƃ����@�����B�O�����̂Ƃ��ẮA��ʂɍ����z�ʎq���́A�����������́A�������q�����́A�C�I������̂Ȃǂɕ��ނ���邪�A���̂������w���͂ɍL�����p����Ă���̂́A�����z�ʎq���̕��тɃC�I������̂ł���B
�@�L�@����́A��ʂɂ̓L���[�g����ƃC�I�������ɓ��� 1�C18-24�j����邪�A�����x�L�@����̏����Ƃ��ẮA�L�m�C�h�\�����`���ł��鍂�x�ɔ��B���� π �d�q�n�i���F�c�j�������A���̗L���ʐς��傫���A�܁E�Z���L���[�g���`���ł���ʒu�ɉ�����\��i��������j�y�ѓd�q���^����i���F�c�j�����Ȃǂ̂ق��A�������̂��������Ղ��Ȃǂ̓�����L����L�T���e���n�A�g���t�F�j�����^���n�A�A�]�n�A�A���g���L�m���n�A�A���U�����n�A�`�A�W���n�A�N�}�����n�A�|���t�B�����n�Ȃǂ̐F�f���ėp����Ă���B
�@�L�T���e���n�F�f�́A�} 1 �Ɏ����悤�Ȋ�{���i���Ƃ邪�A�{�F�f�Q�́A�i1�j�L�m�C�h�\���i�L�m�m�C�h�^�j���`���ł��鍂�x�ɔ��B���� π �d�q�n��L���A���F�c�Ƃ��Ă̗L���ʐς��傫�����߃����z���W���iε�j���傫���A�i2�j�x���[�����_�f�ʼnˋ�����Ă��邽�߁A�_�f���g�̂����L�d�q�ɂ���āA HOMO �G�l���M�[�傳����ƂƂ��ɁA�\������ C��O �Ȃǂ� LUMO �G�l���M�[�����������A���ʂƂ��� HOMO-LUMO �M���b�v���������Ȃ�A�z���ɑ�g�������g���ɃV�t�g����A�i3�j�������n���ł���A�i4�j��������r�I�e�Ղł���A�i5�j���̓Ő������Ȃ��A�Ȃǂ̗D�ꂽ���������ق��A�_���F�f�̃t���I���Z�C���U���̂≖��F�f�ł��郍�[�_�~���U���̂ɑ�\�����悤�ɁA�u�������������̂������A�z���E�u�����ʂ���̒ǐՂ��\�ŁA���͉��w����Ŕėp����Ă���͖̂ܘ_�̂��ƁA����ɂ��̉\���̊g������߂āA�u���C���[�W���O���� 25�C26�j�A��Õ���A���E�G�l���M�[����Ȃǂ̗l�X�ȕ���ɂ����ĉ��p�E���W���W�J����Ă�����ɋ����[���������ł���B
�@�M�҂���L�T���e���n�A�g���t�F�j�����^���n�A�A�]�n�A�A�~���n�Ȃǂ̗L�@����̗��p�ƕ��͉��w�I�n�Ăɂ�葽���̕����̑���@���J�����Ă������A�{�����ɂ����āA�����̂����A�M�҂炪���N�g����Ă����L�T���e���n�A���Ƀt���I�����^�L�T���e���n�F�f�̋z�����x���͂ւ̗��p�ɂ��ďЉ��B
�R�D�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�̍���
3-1�D�t���I���Z�C���̍����ƃL���[�g����Ƃ��Ẵt���I�����^�L�T���e���n�F�f
�@�L�T���e���n�F�f�̍����́A 1871 �N Bayer 27�j�ɂ�閳���t�^���_�ƃ��]���V�m�[���ɉ��������������ėn�Z�k�����ē���ꂽ�t���I���Z�C���̍�������b�ƂȂ�A����ȗ��A�ɂ߂đ����̗U���̂��n�o����Ă���i�} 2�j�B
�@��ʂɁA���q���i���� O�AN�AS �Ȃǂ����L�@����́A�����̔L�d�q���g���ċ����C�I���Ɣz�ʌ��������邱�Ƃ��ł��邪�A���Ɍ܁E�Z���L���[�g���`�����₷���悤�ȕ��q�\���̂Ƃ��̓G���g���s�[����Ȃǂ̃L���[�g���ʂɂ���ċɂ߂Ĉ���ȍ��̂��`������B���̃L���[�g���̂́A�����C�I���Ɗ\�����`������z�ʌ��q�ɂ���āiO�CO�j�z�ʁA�iO�CN�j�z�ʁA�iN�CN�j�z�ʁA�iO�CS�j�z�ʁA�iN�CS�j�z�ʁA�iS�CS�j�z�ʂ� 6 �̃^�C�v�ɕ������A�����C�I���̑I�𐫂͂����� 6 �̃^�C�v�ňقȂ��Ă��邪�A�iO�CO�j�z�ʂ̃L���[�g����́A�قƂ�ǂ��ׂĂ̋����C�I���Ɣ������A�iO�CN�j�z�ʂ̎�������l�̌X��������B
�@����A�t���I���Z�C���́A���̍\����A�C�I�������ɂȂ蓾�邪�A�L���[�g����Ƃ͂����Ȃ��B�L�T���e���n�F�f�ɃL���[�g����Ƃ��Ă̋@�\���������邽�߂ɂ́A�L�T���e�����iO�CO�j�z�ʂ̃J�e�R�[���^�i�W�I�[���^�j�ɂ���̂��ł������I�ȕ��@�ł���A���̖ړI�̂��߂ɂ́A���̓�̃^�C�v�̐F�f�̐v���l������B��́A�} 3 �̂悤�ȃs���K���[�����b�h�iPR�j�ɑ�\����� 4�C5�C6- �g���q�h���L�V�L�T���e��-3- �I���^�i �T �^�j�Ƃ�����̓t�F�j���t���I�����iPF�j�ő�\����� 2�C6�C7- �g���q�h���L�V�L�T���e�� -3- �I���^�i �U �^�A�ȉ��t���I�����^�Ƃ�
��j�ł���B�M�҂�� �T �^�y�� �U �^�̗������g�p���Ă��邪�A �U �^�� �T �^�ɔ�ׁA�z���ɑ�g�����Z�g���ɃV�t�g���邪�A�u������L���Ă���A������ň���ł���A �� ���傫���A��������r�I�e�ՂȂǂ̒���������A�L�@����Ƃ��Ă̗D�ʐ���F�߂Ă���B�{�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�������̌����҂ɂ���č������p����Ă��邪�A�M�҂�́A����܂łقƂ�Ǘ��p���Ȃ������t���I���Z�C���� 2�C7 �ʂɃq�h���L�V������� o- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iOCPF�A�����́A Palatý �� 28�C29�j�̖����ɏ]���āA o- �q�h���L�V�q�h���L�m���t�^���C���A QnPh ���邢�� QP �Ƃ��Ă������A�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�̓��ꖼ�̂Ƃ��� OCPF �Ƃ����j�ɒ��ڂ��A���͉��w�I���p�ɒ��肵���B�����ŁA OCPF �ȊO�̃t���I�����^�L�T���e���n�F�f���n���I�ɍ������A��������X�̕����̕��͂ɉ��p�����B
3-2�DOCPF �̍���
�@Lieberman 30�j�̕��@�ɏ]���āA�܂��A���_���݉��A�����|�_�� 1�C4- �x���]�L�m���� 30 �` 50���Ŕ��������A 1�C2�C4- �x���[���g���I�[���g���A�Z�e�[�g�iTri-Ace�j��31�j�B���ɓ���ꂽ Tri-Ace �Ɩ����t�^���_�����������i�܂��͗��_�A�׃��[���X���z���_�j���݉��A���M�k��������������A�������� 5�� ���_���i�g���E���t�ŗn�����A�h�t�� 30�� �|�_������ pH 4.0 �t�߂ɒ��������B�{�t�𐔏T�Ԓ��x�A��Ï��ɐÒu���A���a�����e OCPF ���h�悵���B�����āA���^�m�[��/�G�^�m�[��/�����A���� OCPF ���i�} 4�j�B
�@�@�@�@[1H-NMR(DMSO-d6, 300 MHz)�Fδ 9.65(s, 1 H), 8.95(s, 1H), 8. 18 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.82(t, 1 H, J = 7.2 Hz), 7.73(t, 1 H, J = 7.2 Hz), 7.42(d, 1H, J = 7.8 Hz), 6.65(s, 2H), 6.00(s, 2H)]
[HRMS(FAB) calcd for C20H13O7 �F 365.0661, Found : 365.0659]
IUPAC ���F2�f 3�f 6�f 7�f -tetrahydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9�f -
[9H]-xanthen]-3-one
3-3�DOCPF�̌����\��
�@�L�T���e���n�F�f�́A���w�v���[�u�Ƃ��ċɂ߂ėL�p�ȋ@�\���F�f�ł��邪�A���̍\���I�m���́A�����w�I��@�ɂ����̂��قƂ�ǂŁA X ���\����͂ɂ�镪�q���̍\���̌���͋ɂ߂ď��Ȃ��B����́A�{�F�f�Q�̍����ɂ�����k�������ɂ���Ă͕��������������₷���A�\���I�Ɍݕψِ��̂����݂��₷���Ȃǂ̂��߁A�����y�ь�����������ł��邱�Ƃ������ƂȂ��Ă���B�M�҂�͍ŋ߁A OCPF �̌������ɐ�������32�j�̂ŁA���̌����\����} 5 �i��j�Ɏ����B���̌��ʁA OCPF �͐����ʂ�A��ɕ��� o- �X���z�t�F�j���t���I�����iSPF�j33�j�y�уt���I���Z�C���i�g���E��34�j�Ɠ��l�ɕ��ʍ\���ł���L�T���e���ƃx���[�����P���������ʍ\����L���Ă���A�ʂ̊p�x�� 69.22�i5�j���ł������B�܂��A�L�T���e���Ɍ������Ă��� 4 �� C-O �����͑S�ē����ł���A�S�� OH ��ł��邱�Ƃ��m�F�ł����B�܂��A COOH ��� C-O�AC��O �����͋�ʂł����A�𗣂��� COO- �^�ƂȂ��Ă���A�} 5�i���j�̂悤�ȍ\���ł��邱�Ƃ����肳�ꂽ�B
�@�@�@ �@�@�@�@3-4�DSPF�̍���
�@Sano35�j�̕��@�ɏ]���āA 3-2 �̑���œ��� Tri-Ace �� o- �x���Y�A���f�q�h�X���z���_�i�g���E�������^���X���z���_���݉��A�G�^�m�[�����A�җ������Ȃ�����M�k��������������A�������� 5�����_���i�g���E���t�ŗn�����A�h�t�� 30���|�_��������_���ɉt�����������B�{�t�� 1 �T�Ԓ��x�A��Ï��ɐÒu���A���a�����e SPF ���h�悵���B�����āA���^�m�[��/�����A���� SPF ���i�} 6�j�B
[1H-NMR(DMSO-d6, 300 MHz) �F 10.2(br, s, 1 H), 8.03(dd, 1 H, J = 8.0, 1.2 Hz), 7.68(td, 1H, J =7.6, 1.2 Hz), 7.60(td, 1H, J =7.6, 1.4
Hz), 7.28(s, 2H), 7.23(dd, 1H, J =7.6, 1.1Hz), 6.65(s,2H)]�B
[HRMS(FAB) calcd for C19H13O7S�F401.0331, Found : 401.0345]
IUPAC ���F[2-(2, 6, 7 - trihydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzenesulphonic acid]
3-5�DOCPF�̌����\��
�@�W���`���X���z�L�V�h�iDMSO�j�F �G�^�m�[���i1 �F 1�j�̍��t���ōČ��������Ƃ���AX ����܂ɑς�����ԐF�j���Ƃ��ē����B����ꂽ�ԐF�j���� ORTEP �}���} 7 �Ɏ������A SPF �́A�L�T���e���ƃx���[���� 1.492 �i2�j Å �̒P�����Ō��������ʍ\���ŁA���̕��ʊԂ̊p�x�� 81.08 �i4�j���Ƃقڒ��s���Ă����B�L�T���e���� 2 �ʁA 3 �ʁA 6 �ʁA 7 �ʂ� 4 �� OH ���L���A C2-O2�C C3-O3�AC6-O6�AC7-O7 �̌��������͂��ꂼ��A1.355�i2�j�A1.332�i2�j�A1.334�i2�j�A1.348�i2�j Å �ŁA 3 �� OH ��ɂ��ꂼ�� DMSO �����f�������`�����Ă����B X ����܂̌��ʂ���A SPF �́A�x���[���X���z���_����̃v���g�����^�ɂ��A�L�T���e�����i�����\���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���������A�t�F�m�[���X���z���t�^���C��36�j�Ɠ��l�A���N�g�����`�����Ȃ��C�I���������X���z������o���C�I���^�ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�B
3-6�D���̑��̃t���I�����^�L�T���e���n�F�f�̍���
�@OCPF �y�� SPF �ȊO�ɍ���������ȃt���I�����^�L�T���e���n�F�f���} 8 ���\ 1 �Ɏ����B�I���g�ʁiX �ʁj�ɃJ���{�L�V���L����3�f�C4�f�C5�f�C6�f - �e�g���t���I�� -o- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iTF.CPF�j�A3�f�C4�f�C5�f�C6�f - �e�g���N���� -o- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iTCl.CPF�j�A3�f�C4�f�C5�f�C6�f-�e�g���u���� -o- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iTBr.CPF�j�́A OCPF �Ɠ��l�A�Y������e�g���n���Q���������t�^���_�� Tri-Ace �����M�k�����������邱�Ƃɂ�蓾�邱�Ƃ��ł����B 4�C5- �W�u���� -o- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iDBr.CPF�j�́A OCPF ��X�|�_���A�L�f�Ƃ̔����ɂ��ړI�̐F�f���B���̑��̃t���I�����^�L�T���e���n�F�f�� m- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iMCPF�j�A p- �J���{�L�V�t�F�j���t���I�����iPCPF�j�A�t�F�j���t���I�����iPF�j�A�T���`���t���I�����iSF�j�A o- �u�����t�F�j���t���I�����iOBPF�j�A�o�j�����t���I�����iVF�j�Ȃǂ́ASPF �Ɠ��l�ASano �̕��@�ɂ�蓾�邱�Ƃ��ł����B
�S�D�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�̋z�����x���͂ւ̉��p
4-1�D���蔽���n�̐v
�@���������t���I�����^�L�T���e���n�F�f���O�����̐��������ɗp���A����ɊE�ʊ����܂ɂ��`�������~�Z���Ɏ�荞�܂��������ōs�킹��A�i1�j�������̐����ɔ��������x���ƒ�F���̂̈��艻�A�i2�j�I�𐫂̌���A�i3�j�~�Z���E�ʂւ̔Z�k���ʂɂ�銴�x�̏㏸�ƈ��萫�̑���A�i4�j�~�Z�����ɐ������̂���荞�܂�邱�Ƃɂ����̐��������̉����A�i5�j���n����F���̂̐����Ɋ�Â��n�}���o���삪�s�v�ƂȂ邱�Ƃɂ���ʑ���̊ȗ����ƍČ����̌���A�i6�j��F���̂̐��n�t���ł̒��a�̖h�~�A�Ȃǂ̌��ʂ����҂ł��ɂ߂ėL���ł���ƍl������1�j�B�܂��A�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�Ƌ����C�I���Ƃ̊Ԃ̒�F���̐��������t���ɁA���̋����C�I���ƍ������\��L���������A�L�@�������̂悤�Ȕ핪�͕��������������邱�Ƃɂ��A�����I�������������N�������A���̌��ʂƂ��Ă̒�F���̂̑ސF�A���Ȃ킿�z���x�̌����𗘗p���镪�͖@�̍l�Ă��A�����������̐��������n�ɂ����ẮA�ɂ߂ėL���ƍl������B
4-2�D���@�������̋z�����x����
�@�L�@�����p���������C�I���̋z�����x���̗͂��j�͌Â��A���܂ő����̕��͖@ 37-40�j������Ă��邪�A 1970 �N����A�z�C�I�����E�ʊ����܂̑�l���A�����j�E�����~�Z���E�ʉ��ɁA�L�@����A�����C�I���y�ё�l���A�����j�E�����Ԃ̎O�����̐���������p�����������ł̋����C�I���̍����x�őI�𐫂ɗD�ꂽ�z�����x�@15�C 16�C 41-45�j���������o�ꂵ���B��ʂɁA�z�C�I�����E�ʊ����܂ƗL�@����p����ƁA��F���̂̈��艻�ɔ����z���т̒��g���V�t�g��A�������̐����ɔ����z�����x�̑���Ȃǂ̌��ʂ��o������ꍇ�������A�ɂ߂ĕ��͉��w�I�ɗL���ƂȂ�̂ŁA���݂������C�I����ʂ̎嗬�ɂȂ��Ă���B�M�҂���z�C�I�����E�ʊ����܁i���邢�͑��̊E�ʊ����܂Ƃ̕��p�ɂ�鍬���~�Z�����j�p���đ����̋����A������̋z�����x�@���J�������B�ȉ��ɁA
�F�f�ʂɕ��ނ��A�i �j���Ɍ������́i�L���j�����z���W���idm3 mol-1 cm-1�j�Ƃ��̕��͖@�ł̎�ȓ����Ȃǂ��������B�܂��A �� ��t���Ă�����̂́A�����I�����������ɂ��z���x�̌����𗘗p�������@�ł���B
�@�����C�I���̒�ʂƂ��āA OCPF ��p���āA�S�i�V�j�i1.7 �~ 105 �����_���ɏՉt46�j�C 1.2 �~ 105 �T�|�j��������47�j�C 1.2 �~ 105 �����u�����t�B���^�[�ߏW�@48�j�j���邢�͑��S�C�I��49�j�i1.3 �~ 105�C ��X�̊ɏՉt���ł� OCPF �ƓS�̑g����/ ESR ����j�A�A���~�j�E���i�V�j�i1.3 �~ 105 �����_���ɏՉt46�j�C 2.1 �~ 105 �����~�Z����50�j�j�A�X�Y�i�W�j51�j�i8.2 �~ 104 �j�A���i�U�j52�j�i1.6 �~ 105 �j�A�����u�f���i�Y�j53�j�i1.3 �~ 105 �j�A�E�����i�Y�j54�j�i9.4 �~ 104 �C OCPF �̎_�𗣎w���j�A�p���W�E���i�U�j55�j�i1.0 �~ 105 ��Z�x�z�C�I�����E�ʊ����܋������j�A�N�����i�Y�j56�j�i1.6 �~ 105 �j�A�}���K���i�U�j57�j�i1.4 �~ 105 �j�A�`�^���i�W�j�i1.9 �~ 105 ��C�I�����E�ʊ����܋�����58�j�C 3.1 �~ 105 �ߎ_�����f������59�j�C 2.2 �~105 �C ���_�����ł� OCPF �̎_�𗣕��t/ OCPF �� Ti �̔������x�萔/����x�萔/�����@�\ 60�j�j�A�n�t�j�E���i�W�j61�j�i1.2 �~ 105�C F-�������j�A�Q���}�j�E���i�W�j62�j�i1.7 �~ 105 �j�A�C���W�E���i�V�j63�j�i1.3 �~ 105 �j�A�X�J���W�E���i�V�j64�j�i1.0 �~ 105 �j�A�o�i�W�E��65�j�i8.7 �~ 104 �A�X�R���r���_�������j�A�K���E���i�V�j66�j�i1.5 �~ 105 �����~�Z�����j�A�R�o���g�i�U�j67�j�i �� 4.2 �~ 108�C H2O2 ������/�����~�Z�����j�A�r�X�}�X�i�V�j68�j�i9.0 �~ 104 �j�A�����i�U�j69�j�i9.2 �~ 104 �L�g�T���������j�A�j�b�P���i�U�j70�j�i9.0 �~ 104 �����~�Z�����j�A���W�E���i�V�j71�j�i7.3 �~ 105 �O�������@�j�A�^���^���i�X�j72�j�i1.0 �~ 105 �j�A�^���^���i�X�j����уj�I�u�i�X�j73�j�i2.2 �~ 105�C 2.0 �~ 105 �����~�Z����/������ʁj�A�K�h���j�E���i�V�j74�j�i1.2 �~ 105 �����~�Z�����j�̕��͖@���J�������B
�@SPF ��p���āA�p���W�E���i�U�j75�j�i1.2 �~ 105 �j�A�Q���}�j�E���i�W�j76�j�i1.7 �~ 105�C �L�@�Q���}�j�E������ʁj�AVF ��p���āA�A���`�����i�X�j77�j�i5.0 �~ 104 �j�A�R�o���g�i�U�j78�j�i1.3 �~ 105�C �V�A�m�R�o���~������ʁj�AMCPF ��p���āA�A���~�j�E���i�V�j79�j�i1.7 �~ 105�C �����̉��P�ƍČ��������j�ASF ��p���āA�W���R�j�E���i�W�j80�j�i1.7 �~ 105 F- �� �� ���j�AOBPF ��p���āA���i�U�j81�j�i3.6 �~ 105 �j���ʂ����B
�@������̒�ʂƂ��āAOCPF �Ɠ��i�U�j��p���� CN-�i �� �j52�j�ASF �ƃW���R�j�E���i�W�j��p���� F- 80�j�i2.1 �~ 105 �j�AOCPF �ƓS�i�V�j��p���郊���_�C�I��82�j�i2.5 �~ 105 �j�ASPF �ƃ`�^���i�W�j��p���� H2O2 83�j�i �� 1.9 �~ 105 �C EDTA �������j�AOCPF �ƃ`�^���i�W�j��p���� H2O284�j�i �� 2.3 �~ 105 �C EDTA ������/�A�_�y�уO���R�[�X����ʁj�B
�@�@�@�@�@
4-3�D�L�@�������̋z�����x����
�@���̐�������i�Ȃǂ̗L�@�������̋z�����x�@ 85-89�j�Ƃ��ẮA�L�@����Ƃ̋��L�����Ő��������F�̂𗘗p������@�A�핪�͕����̎_���Ҍ��\�𗘗p������@�A�핪�͕����̍������\�𗘗p������@�Ȃ�3�j���]����藘�p����Ă��邪�A�������\�𗘗p����z�����x�@�ɂ́A�P�ɋ����C�I�����邢�͗L�@����Ȃǂ̍������܂Ƃ̔����ɂ�萶��������̂̋z���x����ɂ����@���p�����Ă����B���̐�������i�Ȃǂ̗L�@�������́A�����������������̂������A���̕��q���i���ɂ́AO�AN�AS �Ȃǂ����̂ŁA���̔L�d�q���g���ċ����C�I���Ɣz�ʌ��������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�L�@����A�����C�I���y�їL�@�������̎O��
�Ԃł̎O�����̂���������ƍl�����邪�A�O�����̐��������𗘗p�����L�@�������̕��͖@�A���Ȃ킿�L�@����i�������܁j�Ƌ����C�I���p������ʖ@�Ƃ��ẮA���q�z�����x�@ 90�j���m���Ă���݂̂ŁA��������O�����̂̋z���x����ɂ����@�͕���Ă��Ȃ������B�܂��A�O�q�����悤�ɁA�������\��L����L�@�������ƗL�@����̋����C�I���Ƃ̋����I�����������̌��ʂł���z���x�̌����𗘗p������@�����ɗL���ł���ƍl������B
�@�{�O�����̐����������邢�͋����I�����������������蓾�邩�ۂ��́A�g�p����������܂��邢�͔핪�͕������̍�������̐����A���тɎg�p��������C�I���̓����A���Ȃ킿�A�z�ʊ�̉���A�����C�I���̓d�ׁA�C�I�����a�A�z�ʐ��A�d�q�z�u�A����������̂̑傫���ƍ\���ȂǁA��X�̏d�v�Ȉ��q�̑����I�Ȍ��ʂɂ�荶�E����� 1�C 90-94�j�̂ŁA�ǂ̂悤�Ȕ������N���邩��\�����Ĕ����n��v���邱�Ƃ͍���ȏꍇ���������A�핪�͕����̍\���A�������\�AHSAB �� 95�C 96�j�AIrving-Williams ���� 97�j�AMellor-Malley ���� 98�j�Ȃǂ��l�����ċ����C�I����I�����A�L�@����Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��A���Ȃ�̒��x�̔����̗\�����\�ł���ƍl������B�܂��A�������܂Ƃ��ėp����L�@����́A�K�R�I�ɋ����C�I���ɑ������x���������̂��L���ƍl������̂ŁA�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�𒆐S�Ɍ��������B�ȉ��ɁA�J���������i�A���̐����̋z�����x���͂ɂ��āA�F�f�ʂɁA�F�f�Ƌ����C�I���̑g�ݍ��킹���L�ڂ��A�i �j���Ɍ������́i�L���j�����z���W���idm3 mol-1 cm-1�j�Ƃ��̕��͖@�ł̎�ȓ����Ȃǂ��������B�܂��A�� ��t���Ă�����̂́A�����I�����������ɂ��z���x�̌����𗘗p�������@�ł���B
�@OCPF �ƃE�����i�Y�j��p���āA�`�A�~�� 99�j�i4.9 �~ 104 �j�A
�p�p�x���� 100�j�i4.7 �~ 104 �j�A���Z���s�� 101�j�i6.8 �~ 104 �j�A�l�I�}�V���y�уg�u���}�C�V�� 102�j�i1.3 �~ 105�C 1.2 �~ 105 �j�A�Q���^�}�C�V�� 103�j�i4.2 �~ 105 �����u�����t�B���^�[�ߏW�@�j�AOCPF �ƃp���W�E���i�U�j��p����Z�t�@���L�V���y�уA���s�V���� 104�j�i�� 2.4 �~ 105�C 2.9 �~ 105 �j�A�` �I �A �f 105�j�i �� 3.6 �~ 105 �j�A�N �� �A �` �j �� 106�j�i �� 2.3 �~ 105 �j�A5- ���[�h�E���V�� 107�j�i �� 1.1 �~ 105 �j�A�C�\�j�A�W�h 108�j�i�� 6.2 �~ 105�C ��Z�x�z�C�I�����E�ʊ����܋������j�A�O���R�T�~�� 109�j�i �� 8.4 �~ 105�C �A�~�m���ށj�A�A�_ 110�j�i �� 6.5 �~ 105 �j�A�t�@���`�W�� 111�j�i�� 6.3 �~ 105�C �O�A�j�W�m��ܗL�j�A�N�����v���}�W��112�j�i2.2 �~ 104 �j�AOCPF �ƃ}���K���i�U�j��p����X�g���v�g�}�C�V��113�j�i2.4 �~ 105 �j�A�}���C���_�N�����t�F�j���~��114�j�i6.5 �~ 104�C F- �������j�A�����Z�`���s���W�j�E�� 115�j�i3.8 �~ 104�C ������l���A�����j�E�����j�A�N�����w�L�V�W�� 116�j�i5.9 �~ 104�C �a�������ݍ�p/�M�͊w�I�p�����[�^�[�j�A�X�y���~�� 117�j�i1.4 �~ 105�C �A�Z�`���X�y���~�������/ FIA �������j�AOCPF �ƃW���R�j�E���i�W�j��p���鉖���c�{�N������ 118�j�i3.0 �~ 104�C F-�������j�A�~�m�T�C�N���� 119�j�i5.5 �~ 104�C F-�������j�A�x���x���� 120�j�i4.2 �~ 104�C F-�������j�AOCPF �Ɠ��i�U�j��p����X�y���~��121�j�i7.0 �~ 105 �j�A�C���X���� 122�j�i8.2 �~ 104 �j�AOCPF �ƃZ���E���i�W�j��p����X���s���� 123�j�i�� 1.2 �~ 105 �j�AOCPF �ƓS�i�V�j��p����A�f�m�V���O�����_ 124�j�i1.1 �~ 106�C �L�@�����������j�A�N�G���_ 125�j�i3.2 �~ 105�C ��X�̐H�i���j�A�i���W�N�X�_ 126�j�i1.2 �~ 105�C �s���h���J���{���_�j�A�w�p���� 127�j�i4.6 �~ 106�C ���R�����ށj���ʂ����B
�@SPF �ƃE�����i�Y�j��p����q�g�����A���u�~�� 128�j�ȉ� HSA�C 1.6 �~ 106�C HSA ��γ-�O���u�����̒�F�������j�ASPF �ƃ`�^���i�W�j��p���� HSA129�j�i3.4 �~ 106�C �����p�����[�^�[/�M�͊w�I�p�����[�^�[�j�A���^���p�N��130�j 5.2 �~ 106 HSA�j�A�������]�`�[��131�j�i8.3 �~ 105 �j�ASPF �ƓS�i�V�j��p����O���`�����`�� 132�j�i8.3 �~ 105 �j�ASPF �ƃj�I�u�i�X�j / �r�X�}�X�i�V�j��p���� HSA 133�j�i5.2 �~ 106 �j�ASPF �ƃ����u�f���i�Y�j��p����N�����v���}�W�� 134�j�i4.6 �~ 104 �j�ASPF �Ɠ��i�U�j��p����L�j�[�l 135�j�i2.0 �~ 105�C �T�[���N���~�Y���j�ASPF �ƃj�I�u�i�X�j��p���� HSA136�j�i1.7 �~ 106�C �ڎ��@�������j�ASPF �ƃK���E���i�V�j��p����N�����v���}�W��137�j�i1.2 �~ 105 �j�ASPF �ƃ}���K���i�U�j��p����|�����W�� 138�j�i4.2 �~ 106�C ����|���A�~�m�_�j�A DBr.CPF �ƃA���~�j�E���i�V�j��p���� β - �t�F�j���s���r���_ 139�j�i8.4 �~ 104�C �P�g�_�E�q�h���L�V�_�j�APF �ƓS�i�V�j��p����m���G�s�l�t���� 140�j�i1.7 �~ 105�C �J�e�R�[���A�~���j�̒�ʖ@���J�������B
�@TCl.CPF �ƃ}���K���i�U�j��p����v���^�~�� 141�j�i3.6 �~ 105�C ����^���p�N���j�APCPF �ƃ`�^���i�W�j��p���� EDTA 142�j�i �� 2.5 �~ 105 H2O2 �������C �A�~�m�|���J���{���_�ށj�APCPF �ƃ`�^���i�W�j��p����~�m�T�C�N���� 143�j�i1.2 �~ 105 �j�APCPF �ƓS�i�V�j��p����A�X�R���r���_ 144�j�i2.1 �~ 106�C �z�C�I�����E�ʊ����܂� cmc /��F�����@�\�j�ATF.CPF �ƃ}���K���i�U�j��p����q�X�g���i9.0 �~ 105 DNA�����^���p�N�� 145�j�C 9.2 �~ 106 �����u�����t�B���^�[�ߏW�@/�F�ʐF���@146�j�j �Ȃǂ̈��i�A���̐����̒�ʖ@���J�������B
5�D���̑��̋z�����x���͂ƌu�����x���͂ւ̗��p
�@���̑��A�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�ȊO�̐F�f�𗘗p�����z�����x���͂ɂ��āA���M���ׂ����̂����B
�@�L���[�g����Ƃ��Ă� 4�C5�C6- �g���q�h���L�V�L�T���e��-3-�I���^�L�T���e���n�F�f�Ƃ��āA PR �ƃ����u�f���i�Y�j��p���� HSA 147-149�j�i1.4 �~ 106�C���݂̗Տ�����ł̔A�^���p�N����ʖ@�̕W���@�Ƃ��Ċm���j�ANO2- 150�j�i�� 1.0 �~ 105�C���͉��w��菉�_���܁j�A�L���[�g����Ƃ��Ẵg���t�F�j�����^���n�F�f�̃s���J�e�R�[���o�C�I���b�g�ƃX�Y�i�W�j��p����@HSA�@151�j�i3.0 �~ 106 �j�A�N
�����A�Y���[�� B �ƃx�����E���i�U�j��p���� HSA 152�j�i3.8 �~ 106�CFIA �������j�A�L�V���m�[���I�����W�ƃW���R�j�E���i�W�j��p���� HSA 153�j�i�� 8.4 �~ 107�C HSA �ɋɂ߂ē��ٓI�j���ʂ����B
�@�C�I�������Ƃ��Ẵt���I���Z�C���U���̂̃G�I�V���Ƌ�i�T�j��p����A�f�j���i1.1 �~ 105 �A�f�j���ɓ��ٓI154�j�C 3.0 �~ 105 �����u�����t�B���^�[�ߏW�@ 155�j�C�F�ʐF���@������/�C�I�������/�M�͊w�I�p�����[�^�[/�����^�d�q�������ʐ^�j�A�G�I�V���ƃA�f�j����p�����i�T�j156�j�i1.1 �~ 105�C�O�������@������/�C�I�������/�M�͊w�I�p�����[�^�[�j�A�G�I�V���Ƌ�i�T�j�y�уA�f�j����p���郁���J�v�g�v���� 157�j�i �� 3.5 �~ 105�C ���������`�I�[���ށj�A�G�I�V���ƃK���E���i�V�j��p����~�m�T�C�N����158�j�i8.6 �~ 104�C 1.6 �~ 107 �����u�����t�B���^�[�ߏW�@/�F�ʐF���@������/�C�I�������/�M�͊w�I�p�����[�^�[�j�A�t���L�V���ƃ`�A�~����p����p���W�E���i�U�j159�i1.0 �~ 105�C �����u�����t�B���^�[�ߏW�@/�����^�d�q�������ʐ^�j�̒�ʖ@�Ȃǂł���B
�@�Ō�ɁA�t���I�����^�L�T���e���n�F�f�͌u����L����̂ŁA�{����𗘗p���ċ����C�I�����u�����x���͂����B�����̋L�ڂ͊������邪�A��ʂ��������C�I���́A�X�Y�i�W�j�A�o�i�W�E���A�E�����i�Y�j�A�^���O�X�e���i�Y�j�A�S�i�V�j�A�W���R�j�E���i�W�j�A�K���E���i�V�j�A�A���~�j�E���i�V�j�Ȃǂł�������t���I�����^�L�T���e���n�F�f���L���Ă���u���̏����𗘗p�������@�ł���B
�@���̑��L�T���e���n�F�f�֘A�������̌u���ʂւ̗��p�Ƃ��āA�t���I���Z�C���q�h���W�h 160�j��[�_�~�� B �q�h���W�h�iRBH�j 161�j��p���銈���_�f��̌u�����x���́A�t���I���Z�C���ƃ��[�_�~���̍\���I�n�C�u���b�h�̌u���C���[�W���O�v���[�u Rhodol �������iRD�j�̑n�o 162�j�A�F�f���q�̋ÏW�ɂ��u�������傷��A�~�m�x���]�s���L�T���e���n�F�f�Ȃǂ�n�o 163�j�����B�X�ɁA�t���I���Z�C�����������ߒ��𗘗p�����A���f�q�h�ނ̌u�����x���� 164�j�A�t���I���Z�C������ 2�C4- �W�q�h���L�V�x���]�C���������_�i2�C4-DBA�j�𗘗p 165�j�������]���V�m�[���ނ̌u�����x���͂Ȃǂ̕��͖@���J�����Ă���i�} 9�j�B
6�D������
�@����A�M�҂̌������̎�v�e�[�}�ł���u�L�T���e���n�F�f�̗��p�����v�̂����A�L���[�g����Ƃ��Ă̗D�ꂽ������L���Ă���t���I�����^�L�T���e���n�F�f�̍����Ƌ����C�I���A���@���A���̐����A���i�Ȃǂ̋z�����x���͂ւ̉��p�ɂ��ċL�ڂ����B���ɁA�M�҂��l�Ă����~�Z���E�ʉ��A�L�@����Ƌ����C�I���̗��҂�p���鐶�̐����A���i�̕��͖@�A���Ȃ킿�O�����̗��p�@�i�ꍇ�ɂ��l�����̂̐������l������j�́A��ʊ��x�ɂ�����ε �� 105 �ȏ�A�Ƃ��ɂ� 106 �`107 �ɋy�ԋɂ߂č����x���������̂��݂��邪�A���� ε �����ɑ傫���Ȃ闝�R�̈�́A�����q�̔핪�͕����ɑ�������|�F�f���̂̌����T�C�g�����ɂ߂đ傫�����ƂɋN������ƍl������B���̂��Ƃ܂���ƁA�����x����B�����邽�߂ɂ́A�P�ɒ�F���w��̋z���f�ʐς����łȂ��A��F���w��̂����A���Ȃ킿�̐ς��\���l�����邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ����������B�܂��A�������\��L����핪�͕����ƃL���[�g����̋����C�I���ɑ��鋣���I�����������̌��ʂƂ��Ă̒�F���w��̑ސF�A���Ȃ킿�z���x�̌����𗘗p���镪�͖@���A�����C�I���ƃL���[�g���������̂����锽���n�ɂ����ẮA�L�������z���W���iε�j����������ɂȂ�A�ɂ߂ėL���ł���ƍl������B
�@����A�F�f�̍\���I�m�������łȂ��A�����|�F�f���́A�핪�͕����|�����|�F�f�O�����̂Ȃǂ̌����\������̍\���I�l�@�A�L�T���e���n�F�f�̍\���ƌu�����̊֘A���A�~�Z���E�ʉ��ł̋����C�I����L�T���e���n�F�f�̋����┽�����̉𖾂ȂǁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�������B�܂��A�L�T���e���n�F�f�́A��{�I�ɂ̓w�e�����q�̎_�f�A���f���܂ދ����n�L�@�������Ȃ̂ŁAπ �d�q�̎�舵���ɗD��Ă��镪�q�O���@�ɂ��d�q�X�y�N�g���A�G�l���M�[���ʁA�d�q���x���z�Ȃǂ̏��Ɋ�Â��A�������̂̌����̖{���A�������̖��Ȃǂ��𖾂��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�{�e�ŏЉ�������́A�̐X ��j����ȑ�w���_�����̂��x���Ƃ������̂��ƁA����ȑ�w��i���͊w�����A��͉��w�����A�Տ����w�������̃X�^�b�t����ъw���̊F����̋��͂̂��Ƃɍs��ꂽ���̂ł���B���̏�����肵�ĐS��肨��\���グ�܂��B
�@�L�T���e���n�F�f�͌Â�����A��X�̖ʂŃt���I���Z�C���U���̂����łȂ����[�_�~���U���̂��x�X��������Ă��邪�A�܂��܂������̌����ۑ���c���Ă���Â��ĐV�����@�\���L���Ȗ��͂���L�@����ł���A���コ��Ɂu�L�T���e���n�F�f�̗��p�����v���i�W���Ă������Ƃ����҂������B
| ���҃v���t�B�[�� | |
| ���� | ���c �F�� �iYoshikazu Fujita�j |
|---|---|
| ���� | ����ȑ�w�A���M�����w�@�A�T�G����ǁA �O�����[�����e���w�Z |
| �A���� | ��532-0004�@���{���s����搼�{�� 2-3-35-1511 TEL �� FAX �F 06-6391-3343 E-mail �F fujiyoshikazu5@gmail.com |
| �o�g�w�Z | ����ȑ�w |
| �w�� | ��w���m |
| ��啪�� | ���͉��w�A�Տ����w |
| ���݂̌����e�[�} | �a�Ԋ֘A�����̕��͖@�̊J���ƃL�����N�^���[�[�V���� |