 |
| トップページ > サルフェン硫黄検出用新規蛍光プローブとバイオイメージングへの応用 |
 |
サルフェン硫黄検出用新規蛍光プローブとバイオイメージングへの応用株式会社同仁化学研究所 立中 佑希
硫化水素(H2S)は火山性ガスに含まれる無色の気体で、一般的に有毒ガスとして知られる物質である。しかし、1980 年代に硫化水素はラットやヒトで存在することが報告され、一酸化窒素(NO)と一酸化炭素(CO)に次ぐ第三番目のガス性生理活性物質として注目されている。内因性の H2S は、受容体,イオンチャネル,転写因子,酵素などを標的とし、神経伝達調節,平滑筋弛緩,細胞保護,抗炎症,インスリン分泌調節など実に多彩な作用を示すことが確認されている。最近では、生体内で産生された H2S の挙動、その貯蔵や放出のメカニズムも徐々に解明されつつあり、臨床応用への展開も期待されている 1)。 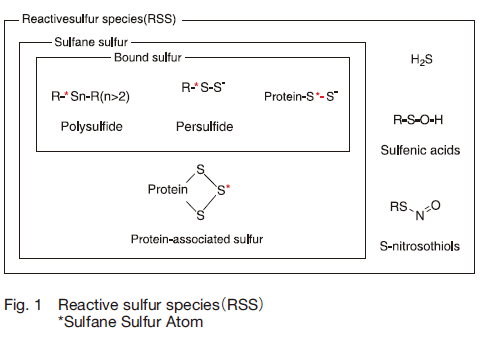 サルフェン硫黄はパーサルファイドやポリサルファイドのように硫黄原子が連結した分子であり、重要な RSS の一つである。これらは、他の硫黄原子に可逆的に結びつく特有な反応性を持っており、最近、これらのサルフェン硫黄が生体内において多様な生理活性を示すことが明らかとなってきている(例えば、トランスファー RNA の転写後修飾を含む補酵素やビタミンの合成、酵素の活性化や阻害など) 3)。興味深いことに、H2S とサルフェン硫黄は生体内において常に共存しており、最近の研究では、H2S 由来のサルフェン硫黄種が、実際のシグナル伝達分子であることを示唆するデータが得られている 4)。このようなサルフェン硫黄研究の関心が高まっているにもかかわらず、生体試料中のサルフェン硫黄濃度の正確かつ信頼性の高い測定法が確立されていないため、それらの産出や作用メカニズムに関する多くの疑問は明確にされずに残ったままである。 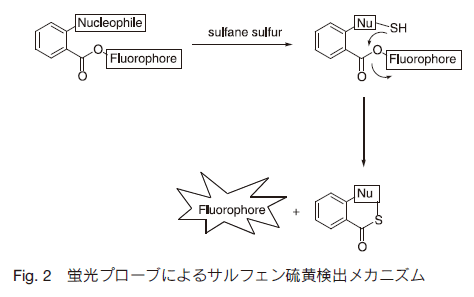 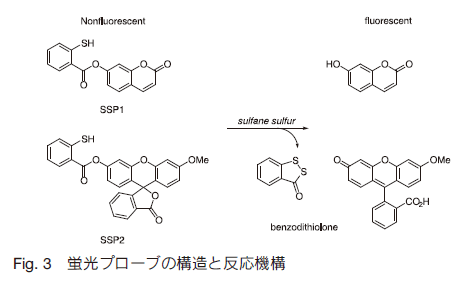 このプローブは、求核性官能基を有するチオサリチル酸と蛍光色素(SSP1: 7- ヒドロキシクマリン, SSP2: フルオレセイン)から構成され、蛍光色素のフェノール性水酸基がチオサリチル酸で保護された状態ではほとんど蛍光を発しない。しかし、これらプローブ内のチオサリチル酸がサルフェン硫黄と反応すると、速やかな分子内環化反応によって benzodithiolone を脱離し、蛍光体を生成する。 SSP1 ,SSP2 は、それぞれ低い蛍光量子収率を示し(SSP1 :φ = 0.06, SSP2 :φ = 0.05)、可視領域に全く吸収特性を示さないが、サルフェン硫黄である Na2S2 を添加すると、蛍光強度は両プローブ共に劇的に増大し、5 分以内に最大蛍光強度に達している(SSP1: 25 倍、SSP2: 50 倍)。これらプローブの検出限界は SSP1: 73 nM, SSP2: 32 nM となり、サルフェン硫黄の高感度検出が可能であることが示唆されている。また、プローブが効果的に機能する pH 領域は、中性から弱塩基性(pH-7~ 8)付近であり、生理的環境下での測定に適している。課題となる選択性に関しても、これらのプローブはシステイン、グルタチオン、ホモシステイン、酸化型グルタチオン、硫化水素、チオ硫酸塩、亜硫酸塩、硫酸塩など他の生物学的硫黄種にはほとんど蛍光変化を示さない上、これら硫黄種が共存する条件下においても Na2S2の添加によって効率的な蛍光強度の増加を示している。以上の結果から、これらのプローブは種々の硫黄分子が複雑に存在する生体試料中においても選択的にサルフェン硫黄を検出できることが示唆される。 硫化水素 生体硫黄マップと試薬選択ガイド硫化水素関連製品群をマップで紹介しています。お役立てください。
参考文献1) R. Wang, Physiol. Rev., 2012, 92, 791. 2) M. C. H. Gruhlke and A. J. Slusarenko, Plant Physiol. Biochem., 2012, 59, 98. 3) J. I. Toohey, Anal. Biochem., 2011, 413, 1. 4) Y. Kimura, Y. Mikami, K. Osumi, M. Tsugane, J. Oka and H. Kimura, FASEB J., 2013, 27, 2451. 5) W. Chen, C. Liu, B. Peng, Y. Zhao, A. Pacheco and M. Xian, Chem. Sci., 2013, 4, 2892
|
| Copyright(c) 1996-2013 DOJINDO LABORATORIES, ALL Rights Reserved. |
