 |
| トップページ > 新しいナノ材料としてのカーボンナノチューブ |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
新連載
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| -最近の展開(バイオからエネルギーまで) ① 中嶋 直敏、藤ヶ谷 剛彦 九州大学 |
今回から 4 回の予定で、「新しいナノ材料としてのカーボンナノチューブ―最近の展開 (バイオからエネルギーまで)― という題目でカーボンナノチューブの基礎物性と最近の応用・展開について解説する(より詳細は、文献 1-2 を参考にしていただきたい)。カーボンはごくありふれた材料であり、人類は古くから用いてきた。カーボンに近年脚光が集まる一因として「ナノテクノロジー」の発展がある。「ナノテクノロジー」とは、ナノスケールの大きさの分子や原子を、「創る」、「組織的に並べる」、「観る」、「操作する」などの手法で、目的の機能を持つナノ物質やデバイス、あるいはシステムを創製制御する科学、技術である。ナノテクノロジーの世界で、 21 世紀の科学技術の鍵物質として期待されているスーパー物質の代表格が、カーボンナノチューブおよびグラフェンである。
1. ナノカーボンとは
ナノサイズの炭素物質をナノカーボンと呼ぶ。フラーレン、カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェン、ダイアモンド様カーボン、カーボンナノクリスタルなどがこれに含まれる(図 1)。また、フラーレンに金属を内包した物質は、金属内包フラーレン、カーボンナノチューブにフラーレンを内包した物質は、フラーレンピーポッドとよばれる。フラーレン、カーボンナノチューブおよびグラフェンは、明確な構造をもっており、次元で分類すれば、それぞれ 0 次元、1 次元、および 2 次元の構造体である。いずれも sp2 炭素から構成されている。これに対してダイアモンドは sp3 炭素構造体である。フラーレン C60 は分子量 720 の低分子化合物であるが、カーボンナノチューブ、グラフェンは、巨大な分子量をもつ電導性「高分子」である。
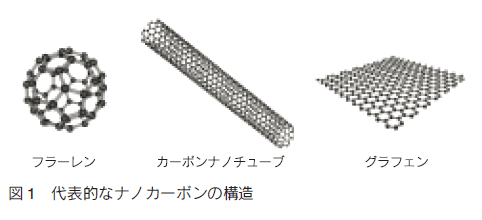
ナノカーボン研究の歴史は「セレンディピティ」(偶然の発見)に満ちている。ナノカーボン研究に火がついたのは、1985 年のフラーレンの発見であった。しかしその 15 年前、大澤は、12 個の正 5 角形と 20 個の正 6 角形をもつサッカーボール分子(C60)を提案した。しかしこれを化学合成する手法は見つからず、C60 の発見までには 15 年の歳月が流れた。 1985 年 Kroto が Smalley らとの共同研究でレーザー蒸発超音速クラスター分子線中にごく微量に存在した C60 を偶然に発見した 3) 。 1990 年、ドイツの Kratschmer らは、C60 の大量合成法(抵抗加熱法)を偶然発見した。フラーレン研究が過熱している中の 1991 年、飯島は、アーク放電法でのフラーレン合成の際の電極の陰極堆積物の中心部分から多層カーボンナノチューブ(Multi-walled Carbon Nanotube; 以下 MWNT)を偶然に発見した。さらに飯島らは 1993 年には単層カーボンナノチューブ(Single-walled Carbon Nanotube; 以下 SWNT)を発見した。 1998 年ルッツイらは、酸処理をした SWNT の内部空間に C60 が内包した物質フラーレン内包 SWNT (ピーポッドという)が生成していることを偶然に発見した。その後、板東ら、片浦らは昇華法で C60 の充填率が高いピーポッドの合成法を確立した。その後、さまざまな分子を内包した SWNT が合成され、特性が研究されている。 1999 年、飯島らはダリヤ状をしたナノカーボン、カーボンナノホーンを偶然発見した。このように、すべて「セレンディピティ」に彩られているのである。化学の歴史が偶然の発見に彩られていることはよく知られている。人間の叡智は、「偶然」により得られるエキサイティングなサイエンスを予知、計画するところまで及ばないということなのであろうか。
2. カーボンナノチューブの構造、特性
CNT はグラフェンシートを円筒状に丸めた構造をしている。円筒が一本のみからなる CNT を SWNT 、直径の異なる 2 本の SWNT が同軸で重なった CNT を 2 層カーボンナノチューブ(Double-walled Carbon Nanotube; 以下 DWNT)、多層に重なった CNT を多層カーボンナノチューブ(MWNT)と呼ぶ(図 2)。 SWNT は直径 0.5 ~ 数 nm とかなり細いが、MWNT は 5 ~ 100 nm である。層数の多い MWNT は細い気相成長炭素繊維(VGCF)と類似するものとみなすことができよう。CNT の合成後の長さは数十 nm から、長いものでは数 mm に及ぶものがあり、合成法により様々な長さ分布を持つ混合物として得られる。

SWNT には、多くの巻き方のタイプが存在し、この巻き方を「カイラリティ」と呼んでいる。合成後の SWNT は様々なカイラリティを持つSWNTの混合物である。カイラリティの違いにより、電気物性、光学物性が少しずつ異なるためにベクトル表示を用いて区別している。SWNT の展開図において原点(基準点)とどの点を重ねるように丸めるかにより一義的に SWNT のタイプを決める方法である。 a ベクトルと b ベクトルを定義し、原点と重なる点を a、b の合成ベクトルで表現する。原点と重ねる点が a 方向に n、b 方向に m 進んだ点だったとき、その SWNT を(n, m)SWNT と 2 つの数字列を用いて表記する。この(n, m)をカイラル指数と呼ぶ。そのいくつかを図 3 に示した。カイラリティの違いにより巻き方や直径が異なることがわかる。(n, m)は SWNT の物性を判断する場合に便利で、例えば n, m が 3 の倍数の時 SWNT は金属性を示し、それ以外は半導体性を示す。また、幾何学的な特徴から(n, n)となる SWNT をアームチェア型、(n, 0)と表記される SWNT をジグザグ型、それ以外の SWNT をらせん型(キラル型)と呼ぶ。
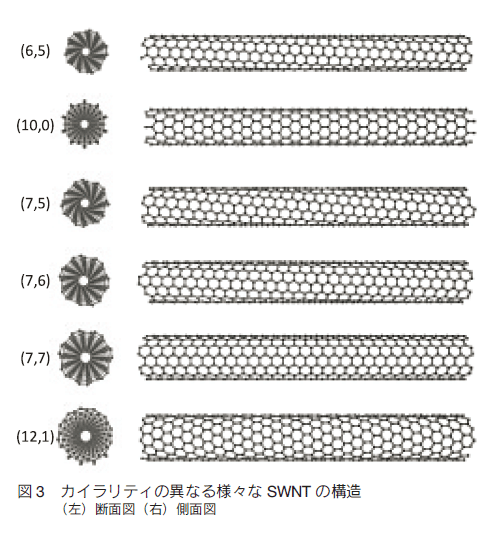
3. CNT の合成
CNT の作製法としては炭素源となるガスを加熱炉にキャリアガスとともに吹き込んで CNT を合成する化学気相成長(CVD)法、グラファイト電極に直流または交流を印加して CNT を成長させるアーク放電法、炭素源となるグラファイトなどをレーザー照射により加熱蒸発させて CNT を得るレーザー蒸発法などがよく用いられる。現在では様々な金属を触媒とした合成法が見出され、大量合成も可能になっており市販で入手できる。アーク放電法で作製される SWNT は結晶化度(SWNT 上にどれだけ欠陥が少ないか)が比較的高く直線性の良い長所があるが、炭素系不純物や触媒粒子を多く含み純度(全生成物量に対する SWNT の量)が低い(~ 30%)のが欠点である。一方、レーザー蒸発法はおよそ 70% 近くまでの高純度な SWNT を合成することができる。レーザー蒸発法で合成される SWNT は、アーク放電法より結晶化度の高く、生成温度の調整が可能なために直径などの制御がアーク放電法より精密にできるという特長がある。しかし出力の高いレーザーを必要とし、一度に得られる量に限度があり、大量生産には不向きである。 CNT の有用性が明らかになるにつれ、大量合成に適した CVD 法が大きな発展を見せている。 CVD 法はもともと 1960 年代に気相成長炭素繊維(VGCF : vapor-grown carbon fiber)の作製で確立された技術であったが、CNT 合成に拡張されていった。
CVD 法には触媒としては主に炭素原料である炭化水素やアルコールを分解する作用を示すことが知られる鉄族(鉄、コバルト、ニッケル)が用いられている。金属ナノ粒子からの CNT 成長のメカニズムは、まず分解された炭素が金属ナノ粒子中に溶解し、過飽和になった後に表面に析出し成長していくと考えられている。
析出初期にフラーレンを半分にしたような構造(キャップ構造)がナノ粒子表面で形成され、そこを始点に炭素が円筒状に析出していくモデル(CNT 成長メカニズム(JST web サイト)が一般的に受け入れられている。
炭素源の分解はプラズマやホットフィラメントで促進させる方法(プラズマ CVD 、ホットフィラメント CVD)もあるが(特に基板を高温にできない場合に有効)、一般的には加熱のみで行い、熱 CVD 法と呼び分けられることもある。 CVD 法の中でも特に研究が盛んなのは、金属微粒子触媒を炭素源ガスの気相中を流動させながら SWNT を成長させる「気相流動法」と、基板上に塗布した金属触媒に炭素源を供給することで成長させる「基板成長法」である。気相流動法は触媒となるフェロセンとチオフェンを用いてベンゼンを熱分解することで得ていた VGCF 製造にルーツを持ち、この方法においてまず MWNT の製造に成功した後、1998 年に中国科学院の Cheng らが SWNT の製造に成功している 4) 。その後、様々な触媒、炭素源、触媒導入方法が検討されたが、市販され世界中の研究者が研究対象として用いているいわゆる HiPco 法が有名である。 HiPco 法は鉄を触媒とし、一酸化炭素を炭素源として成長させる手法で、フラーレンでノーベル賞を受賞した米国ライス大学の Smalley らにより開発された手法である 5) 。
HiPco 法で得られる CNT は残存触媒が多く、およそ 40 wt% 程度の鉄微粒子が残存していて、通常精製して使用する必要がある。
気相流動法の発展における日本のグループの貢献は非常に大きい。
2012 年現在、30 社以上のメーカーが CNT を製造販売している。
それぞれ製造法、直径分布、純度、結晶化度等に差があり、一口に CNT と言っても多様性があることを認識して使わなければならない。表 1 に代表的な CNT メーカー( 2012 年 1 月現在)を挙げた。

4. CNT の基本物性
CNT は直径数ナノメートルでありながら、長さが数マイクロメートルに及ぶ高アスペクト比(~数千)を持ち、sp2 カーボンの強固な化学結合のみから構成されるユニークな構造により非常に優れた機械的強度や、電気伝導度、熱伝導度などを有する(表 2)。一方で炭素のみから構成されるために比重は 1.3 ~ 2.0 g/cm3 程度と鋼の 5 分の 1 程度と非常に軽い。これら CNT 1 本における優れた物性を効率的に材料として反映させ、いかに実用化につなげるかは重要な CNT 研究のターゲットになっている。

4-1. 機械的強度
CNT の大きな魅力の理由の一つとして、優れた機械的強度がまず挙げられる。 SWNT でおよそ弾性率 1 TPa、引っ張り強度 13~53 GPa、破断点伸度 16%、MWNT で弾性率 270~ 950 TPa、引っ張り強度 11~ 150 GPa、破断点伸度 16% と報告されている。これらの値は表 2 に示すように金属材料と比較して優れており、「史上最強」の物質と言って過言ではない。さらに、同じカーボン系材料として、すでに普及し始めている炭素繊維(カーボンファイバー)の物性(弾性率: 900 GPa、引っ張り強度: 6.4 GPa、破断点伸度: 2.2%)と比較しても圧倒的に優れている。
ただし、 CNT は金属材料のように溶融することで任意の形状に成型加工することができないために、直ちに金属の代替材料になるわけではない。
CNT ワイヤーには、SF のようだがその強度と軽量性ゆえ宇宙と地上とを結ぶ「宇宙エレベーター」のワイヤーとしての夢が持たれている。現在では触媒失活と触媒への炭素源拡散の制約上数 mm で止まってしまう CNT の成長を飛躍的に伸ばす技術の登場に期待したい。
CNT を他の材料に添加剤として分散させるアプローチとして、金属、セラミックなどへの添加の他、強度や導電性などにおいて最も補強効果が見込める高分子材料への添加が多く研究されている。高分子との複合体においては高分子材料の特色である軽さ(密度 1 ~ 1.5 g/cm3)を損なうことなく高分子の強度を劇的に向上させられる可能性が高い。理論的には補強により金属系材料に匹敵する強度も実現できるとされている。
金属材料からの置き換えが進めば例えば航空機や自動車の軽量化による燃費向上が見込め、省エネルギー化にも大きく貢献できるであろう。 CNT の極限的性質を複合体に効率的に反映させるためにはまず CNT を高分子中に均一に孤立分散することが重要であることがわかっている。しかし大きなアスペクト比と 1 nm あたり 0.9 eV (計算値)というバンドル形成力を解いて高分子樹脂中均一に分散することが困難なため、理論通りのナノ複合体作製添加効果を得るには至っていないのが現状である。高分子複合体内での分散状態の正確な理解や、界面相互作用の解析などに基づき、用いる高分子ごとに最適な手法を選択することが必要だと考えられている。
4-2. 熱伝導度
金属材料を凌駕する CNT 物性の一つに熱伝導度がある。円筒構造という端のない特徴的な構造から、熱伝導のキャリアであるフォノンの散乱が抑制され、一次元構造上を長距離にわたって熱を伝播させることができる。 SWNT 、MWNT ともに 1 本単独では 3000 W/mK の熱伝導性を示す(理論値 6000 W/mK)。高い熱伝導度を持つ金属である銅でさえ 385 W/mK と一桁低く(ただしバルク固体としての物性)、いかに CNT の熱伝導度が高いかがわかる。このような高い熱伝導度を持つ材料は熱交換器やヒートシンクなどの放熱デバイスとして最近の電子材料分野、自動車、家電分野と様々なデバイスでも注目されている。実際にアルミニウム合金や炭化ケイ素に CNT を添加した放熱材料が開発されている。
4-3. 比表面積
CNT はゼオライトやメソポーラスシリカ等の多孔質材料を上回る大きな比表面積を有し、計算では直径 1.36 nm の SWNT の表面で 1900 m2/g もの表面積がある。合成後にはキャップされている片端を開端して内壁も吸着に寄与できるとすると、合計で 2700 m2/g もの比表面積を与えると見積もられている。一本一本が比較的疎になっている垂直配向 SWNT などにおいては凝集が最小限に抑制できるため、計算値に近い比表面積(2240 m2/g)が得られる。 CNT の大きな比表面積を利用する応用の際には十分に分散した状態で用いることが極めて重要であることがわかる。
4-4. 分光学的性質
CNT は一種の共役系高分子でありその発達したπ共役により吸収が赤外波長域まで拡張している。 SWNT 一本一本は特長ある光吸収挙動を示す。 SWNT においては形状の一次元性のためにバンド構造が量子化したファンホーブ特異点と呼ばれる状態密度が特異的に高いバンドを持っている。これはちょうど低分子化合物における分子軌道と類似の構造で、バンド間遷移に伴う明確な吸収や発光を持つことになる。図 4 に SWNT 分散溶液の吸収スペクトルを示す。発達した共役系のためにバンド間は狭く、半導体性 SWNT におけるエネルギーの最も小さい遷移に対応する吸収(v1 → c1 遷移)は近赤外領域 (800 nm ~ 1600 nm )に現れる。巻き方のわずかな違いによりこのバンド幅が異なるため、様々なカイラリティ SWNT の混合物である SWNT 分散溶液で複数のカイラリティに帰属できるシャープな吸収が観測される。金属性 SWNT の E11 遷移は可視域部に現れるので吸収スペクトルを測定すると SWNT に含まれる金属性 SWNT と半導体性 SWNT の割合も大まかに理解できる。半導体性 SWNT の v1 → c1 遷移も可視域部に現れるため、カイラリティごとに分離した金属性 SWNT および半導体性 SWNT からは様々なそれぞれの吸収に応じた着色が視認できる。 SWNT は、本当は黒くないのである。
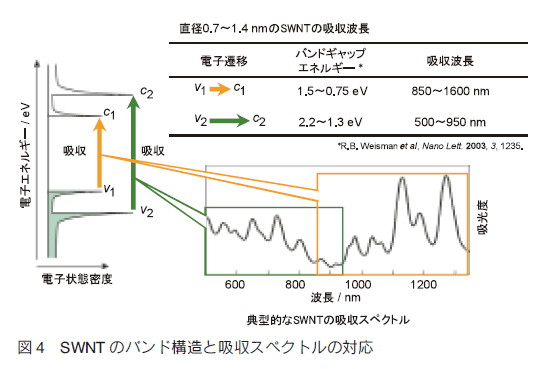
光を吸収して励起された SWNT のうち、半導体 SWNT はバンド間に対応する近赤外発光を伴って緩和する。ただし、 SWNT には蛍光消光剤として作用する金属性 SWNT が共存するために、バンドル状態を解き、完全に孤立分散しないと発光(フォトルミネッセンス, PL)は観察されない。逆に言えば PL の有無により溶液中に孤立分散 SWNT が存在するかが判断できる。
図 5 に SWNT 分散溶液の発光スペクトルを示す。縦軸に励起波長を、横軸に PL 波長を示しており、様々な励起波長における PL スペクトルを順に重ね合わせて上から眺めて高さの差を色のコントラストの差として表現した 2D マッピングである。このようにプロットすることで各カイラリティに由来する発光が個別に観察されることになる。図には帰属も合わせて示してある。含まれる SWNT の直径が比較的小さい HiPco や CoMoCAT は 900~ 1300 nm 付近に PL を示す。この付近の PL は比較的明るいために、レーザーを励起に用いずともインジウムガリウムヒ素(InGaAs)検出器を搭載した分光器であれば検出可能である。
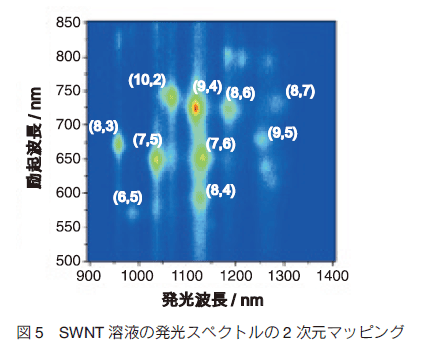
一方、アーク放電法で合成された SWNT は直径が太く(1.2 nm ~)、 PL の量子収率が低く暗いため励起にレーザーが必要となる。
CVD 法由来 SWNT の PL 検出のしやすさは基礎研究に CVD 法 SWNT が好まれる一つの理由である。 SWNT の PL は構造的堅牢さから通常の色素と異なり、ほとんど退色しないことが特長である 6) 。
近赤外領域は血液や水の吸収がなく生体透過性の高い領域であり、この領域に吸収や発光を持ち、退色のない SWNT は生体内プローブなどとして期待されている。ただし、この蛍光量子収率は 3~5% と小さく、ほとんどは無輻射的な過程により失活し熱運動に変換される。逆に、この高い発熱効率を高い熱伝導度と合わせて「分子ヒーター」として光照射による局所的加熱に使うアイデアも生まれてくる。この性質を巧みに利用した CNT のがんに対する温熱療法については後に詳細を紹介する。また SWNT の近赤外域吸収には過飽和吸収という特殊な非線形光学効果があり、近赤外領域が次世代通信帯であることと合わせて次世代光通信材料としての利用も期待されている。
ところで、 PL を示すのは半導体性 SWNT のみであるため、 PL 測定ではサンプルに含まれる金属性 SWNT の情報は得られない。
金属性 SWNT のカイラリティ分布理解のためにはラマン分光法を用いて CNT の直径が振動するモードであるラジアルブリージングモード(RBM)を解析する方法が有効である。図 6 に界面活性剤を用いて水溶液中に孤立分散させた SWNT のラマンスペクトルを示す(励起 785 nm )。 100 ~ 350 cm-1 付近に現れるのが RBM に由来するピークであり、ラマンシフトを ωRBM (cm-1 )とすると直径 d (nm) = 248/ωRBM というシンプルな式で測定している SWNT の直径が求められる。
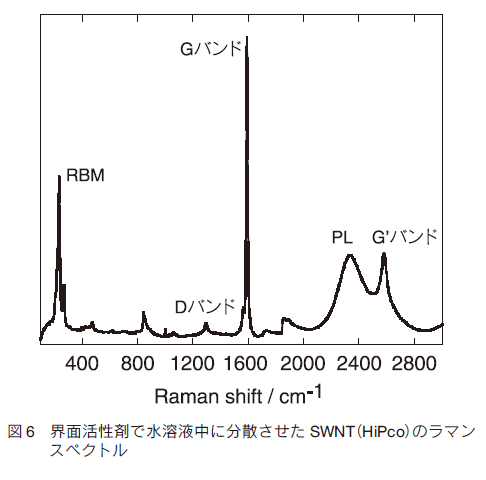
ラマン分光で注意すべき点としては、強いラマン散乱光は物質の光学遷移エネルギーと一致した場合に生じるという共鳴ラマン散乱効果を観測している点である。換言すれば、励起波長に一致する光学遷移エネルギーを持つ SWNT のみを観察しているということである。従って PL と同様サンプル中に含まれる全ての SWNT を見ているわけではなく、多くのカイラリティを網羅的に調べようとする場合、多くの励起波長を使って調べなければならないということになる。図 6 に示すようにラマン分光法では RBM の他、D バンド(1300 cm-1 付近)、G バンド(1590 cm-1)、G’バンド(2700 cm-1)という格子振動に由来する特徴的なピークが現れ、それぞれ有用な情報をもたらしてくれる。G バンドはグラファイト構造中の 6 員環構造の面内伸縮振動に、D バンドはその欠陥構造に由来する。従って G バンドと D バンドの強度比(G/D 比)は CNT 中(グラフェンやグラファイトも)の結晶性の高さを表す指標として極めて有用である。また G バンドはドーピングによってシフトするために、ドープ状態を理解するプローブとなる。G’バンドは D バンドの倍音ピークであるが、比較的強く出るために観察に便利である。外部圧力などによりシフトするために環境に応答したプローブとして使うことができる。また、 SWNT が孤立分散したときに得られる PL が高波数側に観察され、孤立溶解状態か否かをラマン分光測定からも判断できて便利である。
| 著者プロフィール | |
 |
|
| 氏名 | 中嶋 直敏 (なかしま なおとし) |
|---|---|
| 所属 | 九州大学大学院工学研究院 教授 |
| 所在地 | 〒819-0395 福岡市西区元岡 744 番地 TEL & FAX : 092-802-2840 |
| nakashima-tcm@mail.cstm.kyushu-u.ac.jp | |
| URL | http://nakashima.cstm.kyushu-u.ac.jp/jp/ |
| 略歴 |
昭和 55 年 3 月 九州大学大学院工学研究科博士課程単位修得退学 昭和 55 年 4 月 九州大学工学部助手 昭和 57 年 5 月 九州大学工学部助教授 昭和 62 年 5 月 長崎大学工学部助教授 平成 5 年 4 月 長崎大学工学部教授 平成 13 年 4 月 長崎大学大学院生産科学研究科物質科学専攻教授 平成 16 年 4 月 九州大学大学院工学研究院 教授 現在に至る 生まれ、育ちは熊本。趣味はテニス、家庭菜園、スポーツ観戦(テレビ)、雑読など |
| 受賞 | 昭和 61 年 4 月 日本化学会進歩賞(日本化学会)受賞「合成二分子膜の組織化と機能」 平成 12 年 5 月 高分子学会賞受賞(高分子学会)「ナノ分子組織膜を素材とした新電子機能システムの設計・構築」 平成 19 年 9 月 2007 トムソンサイエンステイフィックリサーチフロント Award 受賞(The Thomson Corporation)「カーボンナノチューブ可溶化・機能化デザインへの戦略的なアプローチ」(Strategic Approaches for Carbon Nanotube Solubilization and Functionalization) 平成 22 年 9 月 高分子化学三菱化学賞「カーボンナノチューブ・ポリマーハイブリッド材料のデザイン・創成に関する基礎および応用研究」 |
 |
|
| 氏名 | 藤ヶ谷 剛彦 (ふじがや つよひこ) |
| 所属 | 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 准教授 |
| TEL & FAX | 092-802-2842 |
| fujigaya-tcm@mail.cstm.kyushu-u.ac.jp |
|
| 略歴 |
1995 年 埼玉県立浦和高校卒業 1996 年 東京工業大学工学部第 3 類入学 2000 年 東京工業大学工学部高分子工学科卒業 2002 年 同大学院有機・高分子工学科修士課程修了(上田研究室) 2005 年 東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻博士課程(相田研究室) 2004 年から日本学術振興会特別研究員( 2 年間) 2005 年 米国ノースウェスタン大学 博士研究員(Chad. Mirkin 研) 2006 年 九州大学学術研究員 2007 年 九州大学高等研究院 特任准教授 2011 年 九州大学大学院工学研究科 准教授(現職) |
| 受賞等 | 2003 年 The Photopolymer Science and Technology Best Paper Award 2004 年 日本化学会第 84 春季年会 学生講演賞 2009 年 ポリマー材料フォーラム優秀発表賞 2009 年 高分子学会若手研究奨励賞 |
| Copyright(c) 1996-2013 DOJINDO LABORATORIES, ALL Rights Reserved. |