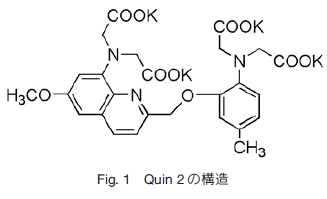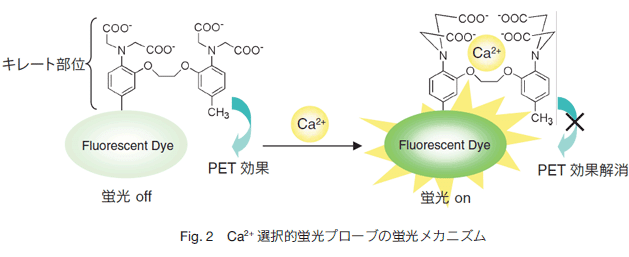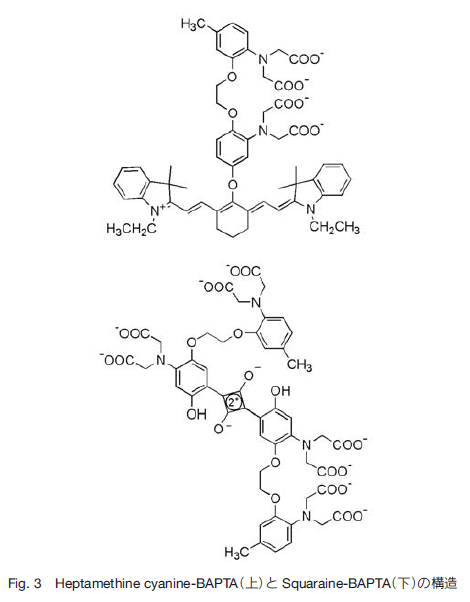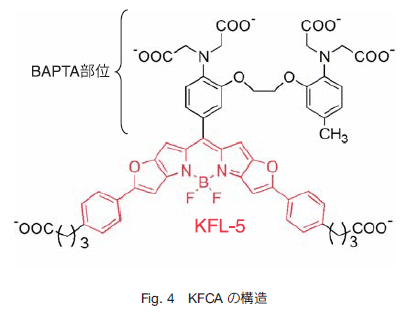新規近赤外蛍光プローブを用いた細胞内カルシウムイオンのマルチカラーイメージング
株式会社同仁化学研究所 田中 智也
カルシウムイオン(Ca2+)は細胞内で情報伝達物質として働き、生命活動を維持する重要なイオンの一つである。細胞内の Ca2+ 濃度は細胞外から様々な刺激を受けることで上昇し、これが引き金となり、次の標的分子に作用する。その結果、神経伝達、筋収縮、内/外分泌系、免疫応答、アポトーシスなど多くの生理作用に関与することが分かっている。このように細胞内 Ca2+ の挙動を知ることは生理現象解明につながることから、細胞内の Ca2+ の分布・挙動は研究の対象として注目され続けている。しかし、その一方で長い間、細胞内での Ca2+ の挙動には不明な点が多く残されていた。これを打破するきっかけとなったのが、1980年代に Tsien らによって開発された Ca2+ 選択的蛍光プローブ Quin 2 (Fig. 1)である 1)。この蛍光色素の登場により、細胞内の Ca2+ の動態や情報伝達物質としての役割の解明に関する研究は大きく進歩したといえる。
Quin 2 のような Ca2+ 選択的蛍光プローブは、 Ca2+ を選択的に認識する Ca2+ キレート部位と蛍光性色素部位の2つから構成されており、 Ca2+ 非存在下では PET(photoinduced electron transfer)効果により蛍光は消光状態にある。しかし、 Ca2+ プローブは一度細胞内に取り込まれると、キレート部位が Ca2+ と錯体を形成し、PET 効果の遮断により、強い蛍光を発する(Fig. 2)。この蛍光強度の変化はカルシウム濃度依存的に起こるため、細胞内の蛍光強度を観察することで細胞内の Ca2+ の動態を視覚的に知ることができる。現在までに Ca2+ 蛍光プローブは蛍光特性、カルシウムイオン解離定数、蛍光安定性等、様々な改良が加えられ、Quin 2 の他に、キレート部位として BAPTA 構造を有する Fura2、Indo1、Fluo3、Fluo 4 などが開発されてきた。
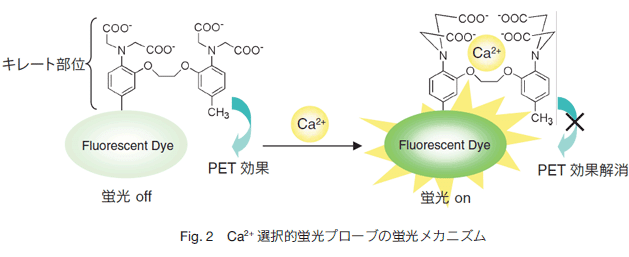
しかしながら、現在までに開発された Ca2+ プローブの多くは可視蛍光色素を利用したものであり、近赤外(near-infrared: NIR: 650〜 900 nm)蛍光色素を利用した Ca2+ プローブについてはほとんど報告されていない。可視光線領域は血液中のヘモグロビンやその他の生体分子の吸収を大きく受け、生体透過性が低いという欠点がある。一方、近赤外線はそれらの吸収を受けず、生体透過性に優れていることから、生体組織の観察に有用とされている。さらに、近赤外蛍光色素は従来の可視蛍光色素と励起波長が異なるため、それらを併用することで細胞内の複数の因子を測定標的とした、細胞内の多重染色への応用が期待されている。これにより、 Ca2+ 濃度の変化とそれに伴う他のイオンや分子の濃度変化を同一細胞内で同時にかつ経時的に観察することが可能になり、細胞内の分子やイオンの挙動をより詳細に知ることができる。
これまでに、Heptamethine cyanine-BAPTA 2)や Squaraine-BAPTA 3)(Fig. 3)のような近赤外色素を基本骨格とした Ca2+ プローブが報告されているが、それらの色素は量子収率が低く、蛍光 ON/OFF シグナル比が小さいという欠点がある。そのため、これらの NIR Ca2+ プローブを細胞内 Ca2+ イメージングに用いた例は報告されていない。
本稿では Suzuki らが開発した新規の NIR Ca2+ プローブ KFCA 4)(λex = 655 nm、λem = 670 nm)を紹介する(Fig. 4)。KFCA はこれまで報告されている NIR Ca2+ プローブと同様に長波長であるだけでなく、 1) 量子収率が高い、 2) 蛍光 ON/OFF シグナル比も一般的に使用されている Fluo 4 などと同等、という利点がある。構造に関しては従来の可視蛍光色素と同様、蛍光色素部位とカルシウム結合部位(BAPTA)の 2 つの部位からなる。蛍光色素部位には BODIPY 骨格を持つ KFL-5 を用いている。KFL-5 は Suzuki らが開発を進めていた KFL ライブラリーの一つで 5,6)、Cy5 とほとんど同じ吸収・蛍光スペクトルを持つことから、基本的な光学装置の使用が可能であり、汎用性に優れている。
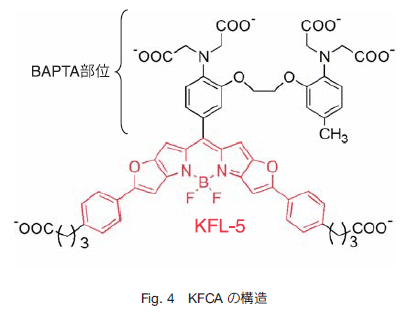
BAPTA と KFL-5 との組み合わせにより、電子密度の高いキレート部位から蛍光色素部位への PET 効果も期待できる。つまり、KFCA は Ca2+ 非存在下では PET 効果により蛍光色素は消光した状態となっているが、 Ca2+ と結合することで BAPTA 部位の電子ドナーとしての能力が弱くなり、 Ca2+ 非存在下に比べて 120 倍の強い蛍光を発する。この蛍光 ON/OFF シグナル比は Fluo 4 のそれと同等であり、Cyanine プローブ(4倍以下)、Squaranine プローブ(3倍)と比べて非常に高い。 Ca2+ との親和性を示す Kd 値も 0.50μM と Fluo 4(Kd = 0.35μM)とほぼ同等であることから、KFCA は Ca2+ プローブとしての蛍光特性を十分に持っている。
次に、Suzuki らは KFCA の Ca2+ プローブとしての性能を評価する為に、HeLa 細胞を用いて Ca2+ のイメージングを行った。その際、細胞内の多重染色の可能性を確認するために、 Ca2+ プローブとして一般的に使用されている緑色系の Fluo 4(λex = 495 nm、λem = 518 nm)と蛍光タンパク質である赤色系の DsRed2 (λex = 558 nm、λem = 583 nm)を KFCA と一緒にそれぞれ同一の細胞内に取り込ませた(DsRed2 は形質転換の際のレポーター遺伝子として使用されている蛍光タンパク質)。その結果、Fluo 4 と KFCA を同時に取り込ませた細胞内において、励起波長と蛍光測定チャネルを変えることでそれぞれに由来する色を単独で観察することができた。蛍光タンパク質である DsRed2 との組み合わせにおいても、Fluo 4 と同様に、励起波長や蛍光測定チャネルを変えることで、同一細胞内でそれぞれの色を観察することができた。これらの結果は KFCA が従来の Ca2+ プローブである Fluo 4 と同様に細胞内でも、その性能を十分に発揮していることを示しているだけでなく、励起・蛍光波長が Fluo 4、DsRed2 の様な可視蛍光プローブと異なるため、細胞内 Ca2+ 濃度変化とそれに伴うその他の生体因子の濃度分布を同時にイメージングすることが可能であることを示している。
さらに、Suzuki らは KFCA と Fluo 4 を同一 HeLa 細胞内に取り込ませた際に ATP 添加による Ca2+ 濃度の経時的変化の観察も行った。その結果、細胞内において KFCA の時間変化に対する蛍光強度の変化は Fluo 4 と同等の挙動を示したことから、 Ca2+ 濃度の経時的変化の観察にも使用できると考えられる。
以上の結果より、KFCA は従来の Ca2+ プローブと同等の性能を持つだけでなく、 Ca2+ 以外の可視領域蛍光プローブ等と併用することで、複数のイオンまたは分子を標的とした Ca2+ の経時的変化の観察への利用が期待される。さらに、KFCA 自体の認識部位を変えることでその他のイオンや活性酸素 (reactive oxygen species: ROS)などの生体分子の多重染色にも応用可能であると考える。
細胞内の応答制御機構を解明するには、複数のイオンまたは分子の挙動を全体的に捉えることが不可欠であり、今後はこのようなコンセプトに基づく蛍光色素の開発が重要になってくるのではないだろうか。
▲ページのトップへ
参考文献
1) R. Y. Tsien, Biochemistry, 1980, 19, 2396.
2) B. Ozmen and E. U. Akkaya, Tetrahedron Lett., 2000, 41, 9185.
3) E. U. Akkaya and S. Turkyilmaz, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 4513.
4) A. Matsui, K. Umezawa, Y. Shindo, T. Fujii, D. Citterio, K. Oka and K.
Suzuki, Chem. Commun., 2011, 47, 10407.
5) K. Umezawa, Y. Nakamura, H. Makino, D. Citterio, K. Suzuki, J. Am.
Chem. Soc., 2008, 130, 1550.
6) K. Umezawa, A. Matsui, Y. Nakamura, D. Citterio, K. Suzuki, Chem. Eur.
J., 2009, 15, 1096.
▲ページのトップへ
|