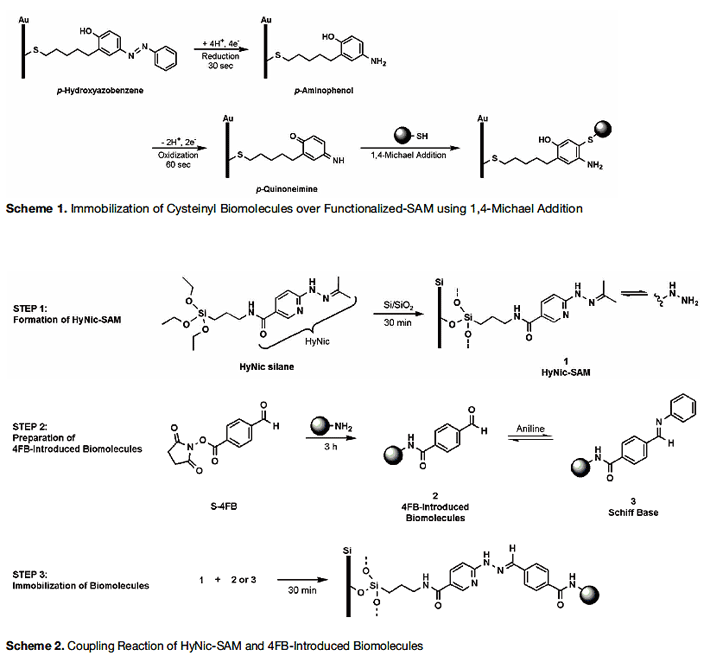盛んに開発が進むバイオセンサー向け生体物質固定化法
株式会社同仁化学研究所 藤野 怜香
現在、生体物質の特異的な機能を物質認識デバイスとして利用し、対象となる物質を検出・定量する方法が、医療、環境、食品分野など幅広く用いられており、センサー部分に抗体、微生物、酵素、細胞などの生体物質を固定化する技術が必要不可欠になっている。特に、特異的反応性を持つ官能基を導入した自己組織化単分子膜(SAM)をセンサー基板上に作製し、生体物質を固定化する手法が多く利用されている。一般に汎用されている固定化方法は、アミンとN-ヒドロキシスクシンイミドエステル、スルフヒドリルとマレイミド、ビオチンとアビジン、アジドとアルキンなどの結合を利用したものである。しかし、これらの方法だけに留まらず、現在もなお利用価値の高い固定化方法の開発が盛んに行われている。そこで本稿では、最近報告された2つの固定化方法について、その手法と有用性について簡単に紹介する。
1.p - キノンイミンとシステインの付加反応を利用した固定化 1)
Jungらは、p-ヒドロキシアゾベンゼンを電気的に還元分解しp-アミノフェノールを生成させ、さらにp-キノンイミンへと電気的に酸化することで、ペプチドなどのシステイン残基を1,4-マイケル付加により固定化する方法を報告した(Scheme 1)。この手法の優れているところは、不活性なSAM 表面を簡単に短時間で活性化できることと、元々生体物質に備わっている反応サイトを利用して固定化できる点である。
過去Jungらは、アゾベンゼンの電気化学的に制御された開裂反応を利用して二段階還元によりアニリンを生成させ、生体物質を固定化する手法を報告した。この手法の改良を続けた結果、アゾベンゼンのパラ位にヒドロキシル基を導入すると、一段階還元で開裂を起こせることがわかった。
そこでJungらは、p-ヒドロキシアゾベンゼンのSAM を作製し、Britton-Robinsonバッファー(pH 2.0)中、-0.3Vの還元電位を30秒かけ、p-アミノフェノールが効率よく生成することを確認した。さらにPBS(pH 7.4)に置換し、+0.3Vの酸化電位を60秒かけ、p-キノンイミンへと酸化すると、システインと速やかに付加反応が起きることを示した。この付加反応はシステイン特異的であり、他のアミノ酸類とは反応が起きないことも確認している。
この固定化法を利用し、基板表面に神経突起の伸長促進物質であるラミニンペプチド:CGG-IKVAVを固定化したところ、2日間の培養を経て、海馬ニューロンの正常な神経突起が伸張していることが確認された。この結果は、マイクロスケールで神経細胞をパターニングできる可能性を示唆しており、脳科学分野の解析に今後応用されることが期待できる。
2.アニリン触媒ヒドラジン-アルデヒド縮合反応を利用した固定化 2)
ヒドラジンとアルデヒドをアニリン存在下反応させると効率よくカップリングが起きることは知られているが、Byeonらは、この反応を様々な条件下で行い、従来の一般的な固定化方法よりも利用価値が高いことを示した。反応スキームをScheme 2に示す。
Byeonらは、マイクロリング共振器でSAM 形成から抗体の固定化、抗原捕捉までをリアルタイムモニターし、HyNic(6-Hydrazinonicotinamide)基と4FB(4-Formylbenzamide)基のカップリング反応条件による反応性の差とセンサー感度を観察した。
まずは、HyNic-SAM と4FB-抗体のカップリングにおけるアニリン触媒のあり/なしの影響と、異なるpH条件(pH 7.4, 6.0, 4.0)による反応効率の差を、固定化された抗体の密度により評価した。
その結果、アニリンが存在する条件では、存在しない時と比較してSAM 表面の抗体密度は4倍も高く、また、酸性側になるほど固定化量が多くなることがわかった。これは、4FBはアニリンが存在するとシッフ塩基を形成し、酸性条件下でより容易にプロトン化し、ヒドラゾン結合を作ることができるためと考えられる。
さらに抗体を導入したセンサーの抗原捕捉能力を測定したところ、アニリンを用いて固定化したセンサーの方が高感度であることがわかった。また、その固定化能力と感度は、一般的なアミンとN-ヒドロキシスクシンイミドエステルを利用した場合よりもはるかに良いというデータも報告している。しかも、カップリング反応にかかる時間は、HyNic-4FBカップリングの方が大幅に短縮できるという利点もある。
固定化反応の効率が低pH側で高かったのに対して、SAM 表面と抗体との非特異的な相互作用(吸着)は高pH側で大きく観測された。この結果が示唆するのは、アニリンを触媒として用いれば、抗体濃度が低い場合、つまり抗体使用量を減らした場合でも、中性付近ではSAM 表面との相互作用により反応サイトが近づくため、固定化効率を上げられる可能性を持っているということである。実際、固定化時に抗体量を減らした場合でも、感度は少々劣るが、抗原の検出が十分に可能なレベルのセンサーを作製することに成功している。今後もさらなる最適化が進められ、より優れた固定化法として汎用されることが期待できる。
以上2つの生体物質固定化方法は、現在盛んに開発が進む固定化方法のひとつにすぎない。今後新たに開発される新手法、また、現在汎用されている方法の改良などにより、高感度で簡便、かつコストパフォーマンスに優れたバイオセンサーを用いた分析技術が飛躍的に発展していくことを期待したい。
▲ページのトップへ
参考文献
1) H. J. Jung, I. Hwang, B. J. Kim, H. Min, H. Yu, T. G. Lee, T. D. Chung, Langmuir, 2010, 26 (19), 15087-15091.
2) J-Y Byeon, F. T. Limpoco, R. C. Bailey, Langmuir, 2010, 26 (19), 15430-15435.
▲ページのトップへ
|