 )錯体化合物とWWHHHHHHタグ(W:トリプトファン、H:ヒスチジン)を利用した場合、錯体化合物のタグ認識に伴い蛍光の大きな変化(蛍光強度の増大と最大蛍光波長のブルーシフト)が観測されることを既に確認している。これは、タンパク質を効率的に蛍光標識するための有用且つ全く新しい技術である。
)錯体化合物とWWHHHHHHタグ(W:トリプトファン、H:ヒスチジン)を利用した場合、錯体化合物のタグ認識に伴い蛍光の大きな変化(蛍光強度の増大と最大蛍光波長のブルーシフト)が観測されることを既に確認している。これは、タンパク質を効率的に蛍光標識するための有用且つ全く新しい技術である。
九州大学と小社は、九州大学での優れた研究成果を迅速に実用化することを目的に組織対応型(包括的)連携契約を締結致しました。下記の技術に関して現在実用化を検討しております。これらにご興味がございましたら小社までお問い合わせ下さい。
No.001 タンパク質蛍光標識技術
タンパク質の蛍光標識技術として、場感受性の蛍光基を結合した新規キレート錯体化合物と新規タグ(通常のヒスチジンタグの近傍に更に疎水性部位を有するアミノ酸を複数個有するペプチドタグ)とを組み合わせて利用する新規な手法を開発した。例としてダンシルアミドとニトリロ三酢酸(NTA)を結合した新規Ni( )錯体化合物とWWHHHHHHタグ(W:トリプトファン、H:ヒスチジン)を利用した場合、錯体化合物のタグ認識に伴い蛍光の大きな変化(蛍光強度の増大と最大蛍光波長のブルーシフト)が観測されることを既に確認している。これは、タンパク質を効率的に蛍光標識するための有用且つ全く新しい技術である。
)錯体化合物とWWHHHHHHタグ(W:トリプトファン、H:ヒスチジン)を利用した場合、錯体化合物のタグ認識に伴い蛍光の大きな変化(蛍光強度の増大と最大蛍光波長のブルーシフト)が観測されることを既に確認している。これは、タンパク質を効率的に蛍光標識するための有用且つ全く新しい技術である。
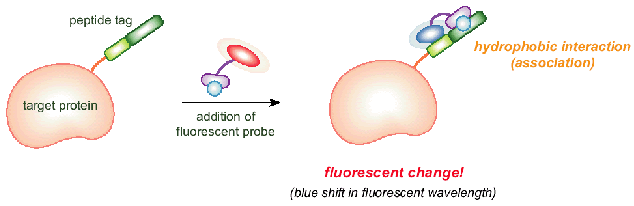 |
No.002 過酸化脂質計測用蛍光試薬
ジフェニルホスフィンのリン原子に対して極めて優れた蛍光特性を有するペリレン類を連結した過酸化脂質計測用蛍光試薬を開発した。例としてジフェニルホスフィンにperylene 3,4,9,10-tetracarboxyl bisimide誘導体を連結した過酸化脂質計測用蛍光試薬を合成し、脂溶性過酸化物であるm-chloroperoxybenzoicacid(MCPBA)を添加したところ、ホスフィンオキシド体の形成に伴い蛍光が大きく増強した。本化合物の蛍光波長は十分に長く(λex=524 nm,λem=535nm in methanol)、DPPPのような短波長励起が必要な従来の過酸化脂質計測用蛍光試薬で問題となる生体試料由来の自家蛍光の影響や生細胞へのダメージを大きく軽減できる。また本化合物の反応体(ホスフィンオキシド体)の蛍光量子収率は極めて高くなっている(〜1 in methanol)。このように本試薬は、過酸化脂質計測用蛍光試薬として非常に優れた特徴を有している。
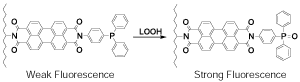 |
 |
 |