 |
| トップページ > 新しいナノ材料としてのカーボンナノチューブ |
 |
|
新連載
|
| -最近の展開(バイオからエネルギーまで) ② 中嶋 直敏、藤ヶ谷 剛彦 九州大学 |
1 . カーボンナノチューブ(CNT)の可溶化
1-1. -可溶化の重要性-
前回紹介したように、CNT は突出した特性、機能をもつ 1 次元導電性分子ナノワイヤーであるが、固体状態ではファンデアワールス力等により束(バンドル)構造体を形成し、水や汎用の溶媒には極めて分散困難である。超音波照射により一部分散するが、水や有機溶媒は CNT を十分に溶媒和できないため、超音波照射を止めると、すぐさまバンドル状態に戻ってしまう。 CNT を可溶化するためには CNT の溶媒和が必要になる。これに対して 2 つの手法を用いる。 1 つは、「化学修飾法(化学修飾可溶化)」でありもう一方は「物理修飾法(物理修飾可溶化)」である(図 1)。
可溶化により CNT の利用、応用は飛躍的に広がる。 CNT の可溶化は CNT の基礎研究、応用研究へのキーサイエンス・テクノロジーとして重要な意味を持つ。
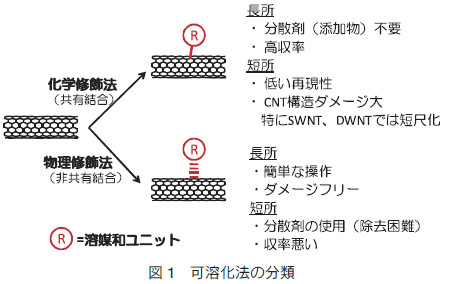
1-2. 一般的な溶媒による分散
可溶化剤なしで CNT を分散できる溶媒がある。 N- メチルピロリドン(NMP)が良く分散できる溶媒である。DMF や DMSO も比較的分散できる。 NMP は CNT のみならず、グラフェンも分散でき、ナノカーボン分散には特別な「マジックソルベント」とも呼べる溶媒である。しかしながら、これら有機溶媒中での分散は一時的なものであり、CNT 長さ等にも依存するが、時間とともに凝集する。したがって安定的な分散には以降に述べる積極的な溶媒和の導入処理が必要となってくる。
1-3. 化学修飾可溶化(共有結合による可溶化処理)
溶媒和を可能にする官能基を共有結合で CNT に導入する手法である。これまでに実に多種多様な化学修飾法が報告されており、すでに総説 1-2) にまとめられているので参照して頂きたい。共有結合による化学修飾は、修飾の度合いにもよるが、CNT を形成する結合を切断するので CNT がもつ本来の性質が失われる可能性がある。

最も一般的なアプローチは、CNT の強酸処理による表面酸化である(図 2)。強酸(H2SO4/HNO3 = 3/1 v/v、40 ~ 70℃)に CNT を加え、超音波(例えばバス型超音波装置)を照射すれば CNT 表面にカルボン酸が導入された酸化 CNT が生成する。導入されたカルボン酸は水への親和性を高め、水への分散を可能にするばかりでなく、さらなる化学修飾の足場とすることもできる。すなわち、酸化 CNT を塩化チオニルと反応させたのち、アルキルアミンやアルキルアルコールと反応させれば、有機溶媒に溶解する化学修飾 CNT が得られる。ポリエチレングリコール等の水溶性官能基を持つアミンやアルコールと反応させれば水に溶解する CNT が合成できる。また、酸化 CNT を足場として重合を行うまたは高分子末端と酸化 CNT を結合させることで CNT/高分子複合体を作製することも可能である。しかし 「過剰の酸化」 による構造欠陥生成に注意が必要である。

酸化 CNT を経由しない置換基導入方法も数多く報告されている。図 3 に挙げた i) カルベンとの反応、 ii) Birch 還元反応による水素化、 iii) [2+1] 双極子付加環化反応(Prato 反応) 、iv) オゾンとの反応、 v) Bingel 反応 、vi)ナイトレンの [2+1] 付加環化反応、vii) アリールジアゾニウム塩との反応、viii) アルキル過酸化物との反応、 ix) アニリンとの反応、x) フッ素との反応(フッ素化)をはじめとして AlCl3 存在下でのクロロホルムの親電子付加反応、Diels-Alder 反応、など多彩な化学修飾などが行われている。簡便な合成法として、クリックケミストリーを利用した CNT の化学修飾も報告されている 3) 。
1-4. 物理修飾可溶化 (非共有結合による可溶化処理)
物理修飾可溶化として、「ミセル可溶化」および「物理吸着可溶化」がある(表 1)。これらに対する総説も多く発表されている 4) 。
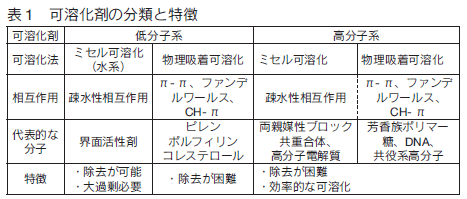
1-4-1. 低分子系可溶化剤
界面活性作用を示す分子はミセル可溶化剤として CNT の可溶化によく用いられる。種々の界面活性剤、例えばドデシル硫酸ナトリウム(SDS)、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム(SDBS)などがよく使われる。膜タンパク質可溶化剤として知られているコール酸ナトリウム(SC)、デオキシコール酸ナトリウム(DOC)などのステロイド系界面活性剤もよく使われる。これらのミセル水溶液中に SWNT を入れ、超音波照射(バス型あるいはチップ型)、次に超遠心機による不溶部の分離(上部の可溶部分のみを回収する)により SWNT 溶解・分散溶液が得られる。一般に 100000 × g 以上の速度で超遠心を行えば、 1 本 1 本分離した孤立溶解 SWNT が調製できる。
一方の物理吸着可溶化剤として、筆者らは多環芳香族基を有する化合物がπ-π相互作用により強く物理吸着し、優れた可溶化剤となると考えた。すなわち、図 4 に示すように、「多環芳香族基に極性基を連結すれば水中での可溶化が、疎水基を連結すれば有機溶媒での可溶化が可能となる」というコンセプトである 5-6) 。

このコンセプトを実証するために、図 5 に示すような、ベンゼン、ナフタレン、フェナンスレン、ピレンを CNT 吸着ユニットとし、極性基としてアンモニウム塩を連結した化合物を合成し、これらを用いて水中での SWNT 可溶化能を調べた。その結果フェニル基、ナフチル基をもつ化合物は可溶化を示さず、フェナンスレンを持つ化合物はわずかに可能化能を示し、ピレンをもつアンモニウム化合物は SWNT を非常によく溶解する、というものであった。その後、多彩なピレン誘導体が合成され、CNT 可溶化に利用されている 4) 。また、その効率的な吸着ゆえ可溶化のみならず、金属ナノ粒子やタンパク質などを CNT に担持する際のリンカー分子としてもピレン誘導体は多く利用されている。

筆者らは、分子と CNT 表面との相互作用の大きさを評価するために SWNT を固定相とする液体クロマトグラフィー用カラムを作製し、様々な多環芳香族分子に対してアフィニティークロマトグラフィーを行った。その結果、図 6 に示すような順列の相互作用の強さを明らかにした 7) 。今後、このような知見が可溶化分子の分子設計に活用できると考え研究を展開している。

また、筆者らは巨大 π 系分子であるポルフィリンも物理吸着可溶化ユニットとして有効であることを世界に先駆けて報告している 8) 。ポルフィリンは光合成中心を担う色素としても知られ、古くから電気化学や光化学の分野において膨大な研究が行われている機能性分子であり、SWNT との組み合わせは光誘起電子移動研究の新素材として展開している。
低分子系の可溶化剤は、多くの場合 CNT 上に吸着している可溶化分子とバルク溶液中で遊離(フリー)の状態にある可溶化分子とが動的な平衡状態にある。従って透析操作などでフリーの可溶化分子を除去すると CNT 上の可溶化分子もやがて減少し、最終的には可溶化分子を失った CNT のバンドル化による析出をもたらすので注意が必要である。
1-4-2. 高分子系可溶化剤
高分子系の可溶化剤も多く報告されており、低分子系と同様にミセル可溶化剤と物理吸着可溶化剤に分類できる 4) 。高分子系物理吸着可溶化剤の場合、多点で CNT 表面と相互作用するために、バルク中に遊離している可溶化剤との交換が遅くなっている点である。耐熱性高分子であるポリベンズイミダゾール(PBI)や電子材料用部材として実用化されているポリイミド(PI)誘導体(図 7)は、DMF などの溶媒中で SWNT を極めて高効率に可溶化する 9) 。 PI/CNT 複合体からは超高強度材料が、PBI/CNT 複合体からは新しい燃料電池触媒が創成できる。

1-4-3. DNA/RNA の利用

CNT 科学において大きな研究領域を形成している高分子系可溶化剤がある。それが DNA である。 2003 年に筆者ら 10) により二本鎖 DNA が(図 8)、また、ほぼ同時に Zheng ら 11) により一本鎖 DNA が SWNT を溶液中に安定に分散させることがそれぞれ報告され、細胞取り込みやドラッグデリバリーシステムなどのバイオアプリケーションを中心として多くの報告がなされている。 DNA による CNT 可溶化は極めて安定で、フリーの DNA を含まない DNA/SWNT 複合体は、1 ヵ月後においても複合体からの DNA の解離は見られない 12) 。 SWNT の孤立溶解に対しては高分子量の DNA である必要はなく、10 量体程度のオリゴ DNA で充分である。高い複合化安定性は、バイオ分野応用研究における多くの成果に役割を果たしている。
2. カーボンナノチューブの電子準位
CNT の発見以来、数多くの研究グループが解明に取り組んできた SWNT の電子準位は、ナノチューブの基本特性のなかでも最も重要な特性であり、ナノチューブ科学の基盤をなす。 SWNT のバンドギャップ、フェルミ準位、仕事関数はカイラル指数に強く依存し SWNT の基礎的な電子特性の理解に不可欠な物理量である。これまでに、走査トンネルマイクロスコピー、酸化還元滴定、ラマン分光電気化学測定などの手法によりカーボンナノチューブの電子特性に関する研究が報告されている 13-14) 。
しかし、ラマンスペクトルや吸収スペクトルでは各カイラリティのスペクトルの重なりが大きいため、個々のカイラリティの電子準位は決定できていない。筆者らは、カイラリティごとに明確なスペクトルが得られる SWNT の蛍光を用いて「その場分光電気化学測定」を行い、ネルンスト式による解析を行ない、各カイラリティの電子準位を実験的に決定できることを示した(表 2) 15) 。
本研究の「その場蛍光分光電気化学測定法」は非常にシンプルな測定法であり、蛍光が検出できるすべての SWNT の電子状態を正確に評価できる。得られた基礎的な実験結果は SWNT を用いたナノデバイスの設計、作製等に対しても重要であり、CNT の基礎科学、物性解明を推し進めるものである。

3. SWNT のカイラリティ分離
3-1. なぜ分離が必要か?
SWNT はカイラル指数(n, m)により決定される幾何構造により、金属性あるいは半導体性となる。 n-m = 3 の倍数の場合は金属性 SWNT に、n-m = 3 の倍数でない場合は半導体性 SWNT となる。これらは、金属系素材、半導体素材として既存物質を凌駕する極めて優れた物性を示すため、これらを用いたデバイス開発等が期待されている。合成法にもよるが、多くの複数のカイラル指数をもつ SWNT 混合物として合成され、金属性 SWNT と半導体性 SWNT の混合物として得られる。合成された SWNT には金属的性質を示す SNNT と、半導体的性質を示す SWNT が 1 : 2 の割合で存在する。
両者を分離するためには、まず SWNT のバンドルをほどき、孤立溶解させることからスタートしなければならない。前述した可溶化の発展がいかに重要であったか理解できよう。可溶化技術の発展により可能になった分離研究の進展を以下に紹介する。
3-2. 半導体性・金属性 SWNT の分離
3-2-1. 化学反応を利用した分離法
金属性 SWNT と半導体性 SWNT を比較すると、金属性 SWNT に存在する自由電子により化学反応性が異なり、金属性 SWNT に優先的に起こる反応が存在する。例えばジクロロカルベン誘導体、ニトロニウムなど様々な付加試薬は金属性 SWNT に優先的に反応させることができる。臭素と SWNT との電荷移動錯体形成は金属性 SWNT で優先的に進行し、わずかに重くなった金属性 SWNT と未反応の半導体性 SWNT の密度差から遠心操作による分離が可能となる。ベンゼンジアゾニウム塩も金属性 SWNT に優先的に付加反応が起こることから、有機溶媒への分散を担うアルキル鎖を持つベンゼンジアゾニウム塩と SWNT を注意深く反応させるとアルキル鎖で修飾された金属性 SWNT が優先的に得られ、有機溶媒への抽出で分離することができる 16) 。同様に、アルキルアミンが金属性 SWNT へ優先的に付加することを利用して金属性 SWNT を抽出した例も報告されている。このように金属性 SWNT への優先的反応の例が多く報告されている中で、半導体性 SWNT への優先的反応およびその反応に基づく分離法も提案されている。その一例として、過酸化水素による酸化溶解は半導体性 SWNT へ優先的に進行し、金属性 SWNT が濃縮される。
これまでに報告されているこれら反応の速度差は小さく、極めて条件を最適化しても、もう一方の SWNT への反応が起こらなくなるわけではない。従って、「分離」というより「濃縮」と言った方が正しい。
3-2-2. クロマトグラフィーを利用した分離法
Krupke らは SDS による可溶化溶液において誘電泳動による金属性、半導体性 SWNT の分離を達成している 17) 。産業総合研究所の片浦らは、アガロースゲル電気泳動(これは DNA の分離に利用されている方法である)で、金属性 SWNT と半導体性 SWNT の分離が可能であることを示した 18) 。この方法では金属性 SWNT のみが泳動するために分離が達成される。後にこの方法は改良され、電場印加なしでアガロースゲルを‘絞る’だけでも金属性 SWNT 溶液が得られることが明らかにされた。彼らはさらにこの方法を発展させ、アガロースゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによる半導体・金属性 SWNT の分離を開発した 19) 。この方法では SDS 分散 SWNT 溶液をカラムに展開させることで金属性 SWNT (純度 ~ 90%)が得られるだけでなく、ゲル中に閉じ込められた半導体性 SWNT を特異的相互作用をもたらさない SDS 溶液で溶出させ半導体性 SWNT 溶液(純度 ~ 95%)も得られることが特長である。このカラム分離法は操作が簡便であり、かつカラムの繰り返し利用も可能で、大量分離への道を拓いた。
3-2-3. 密度勾配超遠心分離(DGU)を利用した分離法
DGU 法は、タンパク質分離法として古くから知られた手法である。 iodixanol やスクロースなど分子量の大きい物質を含む溶液を長時間、超遠心機に施すと沈降とブラウン運動が釣り合う沈降平衡が生じ、密度が液面から底に向かって連続的に変化する。 DGU 法は密度勾配によって試料の沈降速度の差を拡大させ、あるいは遠心力と浮力とがつりあう密度が同じ場所に粒子にバンドを作ることによって、分離を行う方法である(図 9)。 2006 年、米国ノースウェスタン大学の Hersam らはこれをナノチューブの分離に導入した 20) 。 DGU 法で、ステロイド系界面活性剤と、アルキル鎖系界面活性剤の混合ミセル溶液で孤立溶解させた SWNT 水溶液から、金属性 SWCNT と半導体性 SWNT の分離が可能である。純度は高く 99 %に達する。現在ではこの方法で分離されたそれぞれの SWNT が市販されている。しかし、不純物として密度勾配用試薬である iodixanol (コストも高い)を含み、精製が必要という欠点がある。
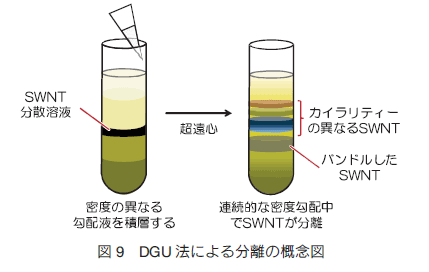
3-2-4. 選択的可溶化法
2007 年に選択的可溶化能を持つ高分子が 2 つのグループからほぼ同時に報告された 21-22) 。どちらもポリフルオレン(polyfluorene; PFO)や PFO 交互共重合ポリマー(図 10)が半導体性 SWNT のみを可溶化するという報告であった。これらの報告は、これまで報告がなかった半導体性 SWNT の高選択的可溶化であったために、非常にセンセーショナルであった。そればかりか、 PFO のアルキル鎖長および交互共重合相手の構造により可溶化する半導体性 SWNT のカイラリティ分布も変化するという極めて興味深い挙動を示した。選択性発現メカニズム、すなわち、なぜ半導体 SWNT のみを認識、溶解するのか謎が多い点がさらに研究者の好奇心を集め、次々と選択性を示す新たな PFO 交互共重合体が報告された(図 10)。

筆者らは PFO ランダム共重合体(図 11)においても選択性を確認し、共重合比によってもカイラリティ分布が変化することを見出した 23) 。 PFO による選択的可溶化には強い溶媒依存性があり、芳香族溶媒であるトルエン、キシレンおよびそれらの類縁体を溶媒として用いた時は選択性が見られるが、その他の溶媒(クロロホルム、THF、アセトン、DMF、DMSO、アルコール、水など)では選択性が発現しない。超分子化学的な分子認識という観点からも非常に興味を魅かれる系である。ただし、収率は極めて低く、大量分取には不向きである。それでも純度の高さは魅力的で、金属性 SWNT の混入のために阻まれていた SWNT の半導体デバイス開発への道を開いたと言える。例えば、半導体性 SWNT は高いオン/オフ比と移動度を持つ電界効果型トランジスタ(FET)の作製へ有望な材料であることが知られているが、未分離 SWNT で作製した FET では金属性 SWNT の存在によりオン/オフ比 102 ~ 103 程度のものしか得られていなかった。しかし、 PFO で分離された半導体性 SWNT はオン/オフ比 > 105 と非常に大きいものであった 24) 。さらに PFO 共重合体の分子設計自由度の高さを利用することで PFO /半導体性 SWNT 複合体に幅広い修飾を施すこともできる。

筆者らは、金属ナノ粒子を担持可能なチオール基やポルフィリン基を持つ PFO 共重合体を合成し(図 12)、金属ナノ粒子を SWNT の長さ方向に沿って配列出来ることを示した。これらを用いて作製した FFT は、オン/オフ比が ~ 105 で、デバイスの移動特性は、金属ナノ粒子の有無で変化することを報告している。最近、ウィスコンシン大学の M. Arnold らは PFO/半導体性 SWNT を太陽電池に組み込むことで近赤外光からのエネルギー取り出しに成功している 25) 。これにより従来の色素では回収できなかった近赤外領域の太陽光エネルギーを回収できることになり、応用は FET にとどまらない。今後の展開に期待できよう。

3-3. 固有のカイラル指数(n, m)をもつ SWNT の分離
DGU 法やゲルクロマトグラフィー法による金属性・半導体性 SWNT の分離は SWNT 分離技術に飛躍的進歩をもたらした。次なる課題は、固有のカイラル指数(n, m)をもつ SWNT の分離(以下、カイラリティ分離と呼ぶ)である。 SWNT の直径の差や構造的な差異は極めてわずかであり SWNT 発見当時に存在した既存分離精製技術にはこれらを分別できそうな技術はないと思われていた。それではこれらの分離精製にはどのような戦略で臨んできたか、以下に解説する。
3-3-1. クロマトグラフィーの利用
Zheng らは、表 3 に示したように、配列の異なるオリゴ DNA を精密設計、合成し、イオン交換とサイズ排除の二つのカラムクロマトグラフィーを併用することによって、12 種の半導体 SWNT および 2 種の金属性 SWNT の単一カイラリティ(n, m) SWNT の分離に成功している 26) 。特に(6, 6)、(7, 7) SWNT はこれまでに単一カイラリティ分離がなされていなかった金属性の SWNT であり、これらの分光特性が明らかにするための貴重な素材を提供した。また、片浦らは、第 5 章 2C で述べたアガロースゲルによる半導体・金属性 SWNT の分離をさらに発展させ、デキストラン系ゲルを充填したカラムを多段階にし、さらに導入する量を調整することでカイラリティ分離を達成した。このように、CNT のわずか数オングストロームの直径の差と、これに起因する構造の違いを認識分離する分子が存在するという事実は極めて興味深い。

3-3-2. 密度勾配超遠心分離(DGU)法の利用
前述した DGU 法が有効である。たとえば、 iodixanol を密度勾配培地として用い、コール酸ナトリウムで可溶化した SWCNT の密度勾配遠心を三回繰り返すことで、97% が直径誤差 0.2 nm 以内の(6, 5),(8, 3)および(9, 1) SWNT を含む溶液を得ることができる。 DGU 法の分離の原理は、界面活性剤等で可溶化した SWNT の密度の差を利用することであり、 SWNT 直径の差が小さい、たとえば(6, 5) SWNT (直径 0.76 nm)と(8, 3) SWNT (直径 0.78 nm)の密度はほぼ等しく、これらの分離は困難である。筆者らは、SWNT のレドックス機能に着目した。(n, m) SWNT は固有の電子状態を持っており、それぞれ酸化還元電位が異なる 27) 。
一方、塩化金酸は SWCNT と反応すると表面に金として還元析出することが知られている。塩化金酸と SWNT を反応させると、(6, 5) SWNT 以外の SWNT は、塩化金酸を還元することができ、金ナノ粒子が SWNT 表面に形成される。ところが、(6, 5) SWNT ではこのような還元反応が進行しない(図 13)。結果として、(6, 5) SWNT とそれ以外の金ナノ粒子吸着 SWNT に「重さ」の差が生じる。この結果、これらの溶液に DGU を行なうことにより、高純度で(6, 5) SWNT を単離できる。
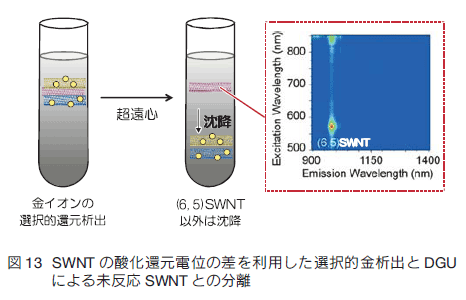
ライス大学の Weisman らは DGU 法を発展させ、非平衡非線形の密度勾配を作り、これを用いて従来の DGU よりさらに高純度な(n, m)カイラリティ分離を可能にした 28) 。 Weisman らの報告は、遠心操作後に(n, m) SWNT それぞれの等密度点ができる限り離れるような非線形の勾配を用いて、多くの(n, m) SWNT を一回の操作により分離する方法である。この方法で彼らは、10 種類のカイラリティの SWNT を高純度分離した。
3-3-3. 選択的可溶化法
いくつかの可溶化剤では特定のカイラリティを優先的に可溶化することが知られている。前述した半導体性 SWNT 選択的可溶化能を示す PFO 可溶化においてもいくつかの系で 1 つのカイラリティをもつ SWNT の濃縮が達成されている。筆者らは図 11 で示したランダム共重合体において嵩高い置換基をもつ PFO 基が増加するにつれて、可溶化できる SWNT のカイラル角が小さくなる傾向に気づいた 29) 。モノマー構造やその共重合比と可溶化される SWNT カイラリティとの相関をさらに精密化することにより、任意のカイラリティの SWNT を選択的に認識、分離できる PFO 誘導体が合成できるかもしれない。
3-3-4. エナンチオマー分離
キラル型に分類される SWNT には互いにエナンチオマーの関係をなす右巻き SWNT と左巻き SWNT が存在する。両者の間で電子物性の差は見い出されていないが、これらを分離することは、純粋な科学的興味から興味が持たれる。この目的においても上述した各種分離法が駆使されている。いち早くエナンチオマー分離を達成したのは、選択的可溶化法であった。小松らはポルフィリンピンセットと呼ばれる 2 つのポルフィリンのなす角度の固定されたポルフィリン 2 量体による SWNT 可溶化において、ポルフィリン側鎖にキラルユニットを導入することでエナンチオマー分離を達成した。この結果は、ポルフィリンの π スタッキングだけでなく、側鎖も SWNT 表面を認識していることを端的に示す点でも興味深い。また、Weisman の非線形 DGU 法では、不斉をもつコール酸誘導体で可溶化された右巻き SWNT と左巻き SWNT が異なる密度を示すため、異なるバンドとして分離することができる。この方法では 7 種類のキラル型 SWNT の光学分割に成功している 30) 我々は、バルキーなキラル基を持つ PFO 誘導体を分子設計、合成し、これにより、半導体性のみの右巻き/左巻き SWNT の分離に成功した 31) 。
| Copyright(c) 1996-2013 DOJINDO LABORATORIES, ALL Rights Reserved. |