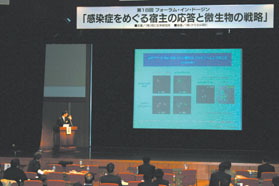|
| トップページ > 感染症をめぐる宿主の応答と微生物の戦略 |
 |
|||||||||||||
感染症をめぐる宿主の応答と微生物の戦略
今回、2007年11月30日に開催いたしましたフォーラム・イン・ドージンは多くの皆様に盛況をいただきました。すばらしいご講演をいただきましたが、ご聴講いただけるのは一部の方のみになります。
そこで、今回 金沢大学 中西義信先生に本テーマをまとめていただましたので、皆様にご紹介させていただきます。 1.はじめに表題と同じタイトルを掲げて、第18回フォーラム・イン・ドージンが2007年11月30日に熊本市で開催された。本フォーラムは株式会社同仁化学研究所の全面的な支援のもとに毎年行われており、今年は岩永貞昭氏(九州大学名誉教授)の発案を受けて、山本哲朗氏(熊本大学教授)が代表世話人、住本英樹氏(九州大学教授)と中西が当番世話人となって企画・実行された。本稿では、今回のフォーラムでのテーマについて、当日に討論された内容を中心として考察する。 2.背景私たち人類は、共存関係にある微生物の影響を陰に陽に受けている。陰の部分は感染症であり、食中毒や風邪のような“見慣れた”病気から、新興感染症や再興感染症に分類される“見慣れない”病気まで、さまざまな疾病が微生物の体内への侵入を原因として引き起こされる。私たちの体には感染症を防止するための生体機能が備わっており、深刻な感染症が発症することはまれである。しかし、感染した微生物の量が多かったり、毒性が強い微生物の侵入を受けると、死に至る事態が発生する場合がある。そうなると医療の力を借りることになるが、残念ながら多くの微生物については“特効薬”などの決定的な医療はまだ存在しない。 これまで開発されてきた抗感染症薬の多くは、抗生物質に代表される微生物側に働く化学療法剤である。しかし、そのような薬にさらされた微生物は、遺伝子発現様式や遺伝子構造そのものを変化させて、薬剤耐性を獲得する。これは「薬を使うほど耐性微生物が出現する」ことを意味し、抗感染症薬の賢い使い方が求められている。抗感染症薬の多くは、微生物の増殖や生存に必須な反応に関わる微生物固有のタンパク質の働きを阻害する。反応の種類や標的タンパク質がその反応の中でどの段階に関わるかよって、耐性微生物が出現しにくい場合のあることが知られる。これは、微生物側の新たな標的を見つければより有効な薬の開発につながる可能性があることを示す。一方、微生物側ではなく宿主の生体防御システムを標的とする抗感染症薬も存在する。既存のそのような薬は、微生物成分を含むものか、たまたま見つかってきた天然物由来の生理活性物質がほとんどである。抗感染症薬開発のためのもうひとつの努力は、標的を具体的に絞ってこのようなBiological Response Modifiers(BRM)を探索することであろう。また、感染症の予防の面ではワクチンによる医療がある。しかし、形状がどのようであれワクチンには副作用がつきまとうし、微生物の中には頻繁に抗原性を変化させて免疫を逃れるものが多く存在する。いずれにせよ、感染症に対する有効な医療を開発するためには、宿主に侵入した微生物の巧妙な振る舞い及びより賢いはずの宿主が有する防御システムを詳しく知ることが必要である。 3.知識の整理3. 1. 宿主の生体防御システム私たちの体を感染症から守ってくれるのは免疫である。免疫は大きく自然免疫と獲得免疫のふたつのシステムから成り、それぞれに免疫細胞が活躍する細胞性反応と免疫関連タンパク質が主に働く液性反応が含まれる。侵入微生物を感知して最初に誘導されるのが自然免疫であり、その反応を介して活性化されるのが獲得免疫である。自然免疫では微生物個々ではなく特定集団の微生物(グラム陰性細菌など)が共通に持つ構造(パターン)が対応する受容体に認識されるのに対して、獲得免疫では個々の微生物に存在する特定分子の一部(抗原)がその受容体(抗体)に認識されて微生物の侵入が感知される。さらに、獲得免疫では同一抗原の再度の侵入に対しては迅速かつ強大な免疫応答が起こることが知られる。しかし、自然免疫と獲得免疫との間のこのような違いは少々怪しくなりつつある(後述)。獲得免疫による応答は、同一抗原を有する微生物の二度目以降の侵入の際に有効であり、実質的には最初の侵入時ではそのための準備を整える意味しか持たない。したがって、宿主が初めて遭遇する抗原だけを持つ病原性微生物が体内に入ってきた時には、自然免疫がしっかり働いてくれなければ病気になってしまう。 呼吸器官または消化器官に入った微生物は、その場に存在する免疫細胞や抗微生物物質の働きにより、多くの場合は除去される。しかし何らかの理由でその防御を逃れた微生物の一部は、上皮細胞のバリアを破って体内に侵入して血液に入り込む。そうすると、血液中の免疫細胞がそれら微生物を感知して宿主の防御反応が誘導される。これは、免疫細胞が特殊なタンパク質を使って微生物物質を認識することで起こる。最初に起こる自然免疫では、抗微生物物質の生産、補体の活性化、そして微生物の貪食除去などの反応が起こる。自然免疫反応は同時に獲得免疫の活性化を導き、侵入した微生物の抗原に対する特異的な抗体を生産できるように、リンパ球に質的及び量的な変化を促す。具体的には、樹状細胞を代表とする免疫細胞が何らかの経路で微生物物質を獲得し、そこに含まれる抗原となる構造物をTリンパ球に提示する。微生物物質の刺激を受けたTリンパ球は、それ自体が微生物殺傷機能を獲得したり、他のリンパ球を刺激するタンパク質を放出したりする。この後者の反応は、Bリンパ球による特定抗体の生産準備を促すと同時に増殖を活発化させる。これが、同一微生物の再度の侵入に備えた準備である。同じ抗原を持つ微生物が再度侵入してきたら、変化したBリンパ球が刺激されて強力な抗体が速やかにかつ大量に作られ、侵入微生物が除去される。 3. 2. 微生物の抵抗と宿主の対抗微生物は宿主の防御反応を回避して、私たちの体内で何とか生き延びようとする。ある種の細菌は、自分の表面構造を変化させて免疫細胞による感知を逃れる術を持つ。またあるものは、たとえ感知されても免疫細胞内での防御反応誘導経路を阻害することができる。微生物が免疫細胞に貪食されることは宿主の防御機構のひとつであるが、細菌の中には自ら免疫細胞の中に入り込もうとするものもいる。しかも、通常は起こる殺菌や消化を逃れて、免疫細胞内で生存を続けるのである。細菌はこのようにして、補体、リンパ球及び抗体の攻撃から逃れることができる。さらには、獲得免疫誘導のための抗原提示を阻害する微生物も存在する。 このような微生物の抵抗に対して宿主側も黙ってはいない。免疫細胞に自ら入り込んで生存を続ける細菌を、通常とは違うやり方で殺傷する仕組みがある。それはオートファジーと呼ばれ、細胞内の細菌が膜で包まれて分解されてしまう反応である。もうひとつの宿主の逆襲はアポトーシスの誘導である。一般に、アポトーシス細胞は貪食によって除去される。微生物の入り込んだ細胞がアポトーシスを起こすと、貪食されて宿主細胞もろとも微生物が消化されてしまう。これは、“身を切らせて骨を切る”宿主の戦法と言える。 4.2007年フォーラムの内容侵入微生物に対する宿主の免疫応答機構は、先に述べたように大まかな部分はほぼ判明していると言ってよい。ただし、“微生物感染でなぜ病気になるか”はまだよく分かっておらず、より詳細な機構の解明、特に免疫誘導と病原性発揮にかかわる微生物側及び宿主側の因子を同定することが必要である。それを達成することにより、感染症発症の仕組みが明らかになるとともに、より有効なワクチンや抗感染症薬の開発が可能になると思われる。本フォーラムでの講演のすべてが、それにつながる可能性を与えてくれる研究成果を発表するものであった。 4. 1. 免疫応答機構の研究侵入微生物を感知する仕組みには、変化を増大させてより効果的な応答を起こすためのトリックが隠されていることが明らかにされた。この結果は、韓国釜山国立大学薬学部の李福律(Bok Luel Lee)氏による昆虫を用いた研究により示された。ショウジョウバエを使った研究で明らかにされた昆虫の免疫応答システムは微生物の種類により使い分けられる2つの経路から成り、そのうちの少なくとも1経路では体液(血液に相当)中に存在するタンパク質の働きが必要であることが分かっていた。李氏の研究グループは、幼虫の体液からその経路を構成するタンパク質群を精製し、それらを使って微生物表面物質から免疫細胞受容体につながる経路を無細胞反応系で再現させることに成功した。新しく見出された2種のタンパク質はいずれもタンパク質分解酵素であり、この経路での主反応はタンパク質部分分解の連続反応であることが示された。タンパク質分解酵素の連続した活性化によって、微生物物質の感知という情報が体液中で増幅されるわけである。最後に活性化された酵素が体液中に存在する特定の宿主タンパク質を部分分解すると、その産物がリガンドとなって免疫細胞の受容体に結合して免疫反応を引き起こす。このように、昆虫での2つの免疫応答経路のうちのひとつが完全に明らかになったわけである。哺乳類では、補体活性化、血液凝固及びアポトーシスという3つの現象の誘導経路がタンパク質部分分解の連続反応で構成されていることが知られる。哺乳類でもこのプロテアーゼカスケイドが侵入微生物の感知に使われているかどうか、今後の解析が待たれる。 獲得免疫ではリンパ球が重要な役割を演じる。リンパ球の働き方については、表層に存在する種々の受容体の解析は進められているものの、それ以外の分子の同定と機能解明は遅れている。九州大学生体防御医学研究所の福井宣規氏は、リンパ球での細胞骨格構造を制御する新しい分子を見出してその役割を調べた。細胞の動きや形態変化には細胞骨格の再編成が必要であり、それにはある種の低分子量Gタンパク質の働きが必要であることが知られる。Gタンパク質の活性化はそこに結合するグアニンヌクレオチドがGDPからGTPに置き換わることで行われ、グアニンヌクレオチド交換因子(GEF)と呼ばれるタンパク質がその反応を規定する。福井氏はリンパ球が移動する際に働くGEFがDOCK2という分子であることをつきとめた。DOCK2が作られないようにしたリンパ球は、体内での免疫応答のための移動速度ばかりか、抗原を認識する機能も低下することが分かった。後者は、細胞骨格構造変化が妨げられて抗原認識に必要な分子の細胞表層への移行が滞ったためと推測された。さらに、DOCK2を持たないマウスでは、免疫機能が低下したために起こるさまざまな不具合が生じていた。別の白血球である好中球は、哺乳類において侵入微生物を貪食除去する主役である。好中球は微生物侵入を感知した免疫細胞からの情報を得て、リンパ球の場合と同様の原理で侵入場所に移動する。細胞骨格の構造変化を導く低分子量Gタンパク質の働きには、ある種のホスホイノシタイドが必要である。ホスホイノシタイドは、リン酸化の場所の違いによって異なる反応を引き起こす情報伝達物質である。そのリン酸化を規定する酵素のうち、ホスホイノシタイド3-キナーゼ(PI3K)は4位と5位がリン酸化されたホスホイノシタイドのさらに3位をリン酸化する酵素である。好中球は4種のPI3Kアイソザイムを有しており、それらの使い分けはまだよく分かっていなかった。佐々木雅彦氏(秋田大学医学部)はノックアウトマウスを解析することにより、PI3Kγと呼ばれるアイソザイムが好中球の微生物侵入部位への移動に必要であることを明らかにした。好中球による免疫反応は微生物除去には必要であるが、それによって起こる炎症は人体に傷害を与える。本研究成果は、PI3Kγが新しい抗炎症薬を開発する際の標的分子となりうることを示す。 侵入場所にやってきた好中球の貪食作用により、微生物は貪食胞として好中球内部に取り込まれる。すると、貪食胞内部に活性酸素が生産されて微生物は殺される。この活性酸素生産を規定するのがNADPHオキシダーゼと呼ばれる酵素である。この酵素は多数のサブユニットから成り、微生物を含んだ貪食胞が形成されると、その膜内でサブユニットが集合して酵素活性を発揮する複合体が作られる。このサブユニット集合の仕組みはまだよく分かっておらず、住本英樹氏(九州大学生体防御医学研究所)はその研究に取り組んでいる。本講演では、微生物貪食をきっかけとして活性化されたp47サブユニットの働きで他のサブユニットが集合する仕組みに関する研究成果が報告された。微生物の中には、免疫細胞内でNADPHオキシダーゼ複合体の形成を妨げて活性酸素による殺傷を逃れるものが知られる。住本氏の研究はその仕組みの解明につながると期待される。 4. 2. 病原性発揮機構の研究感染症の原因は“病原性”を有する微生物が体内に侵入することであるのは明らかだが、それがどのようにして発症につながるかはよく分かっていない。破傷風菌やボツリヌス菌など明らかな毒素を持つ微生物によるものを除くと、感染症での病態は宿主の免疫が過剰になった結果だとする考え方がある(後述)。この問題への答を得るためには、微生物を感染させた動物での免疫反応の程度と病態の進行度を調べる実験が必要である。帯広畜産大学原虫病研究センターの嘉糠洋陸氏は、遺伝学が活用できる昆虫を用いてそのような研究を行っている。嘉糠氏は、さまざまな種類のショウジョウバエに微生物を感染させ、抗微生物物質の生産と致死性の程度を比較した。その結果、ハエの種類によって免疫応答の程度と死ぬまでの時間が異なり、長く生きるハエでは免疫応答が早く起こることが分かった。また、1種類のハエの中でさまざまな遺伝子の発現を人為的に高め、それらに微生物を感染させて発症の程度を調べる実験も行われつつある。嘉糠氏はショウジョウバエのすべての遺伝子について感染抵抗性への関与の有無を調べることをめざしており、その研究の完了はそれほど遠くではなそうである。既に、抵抗性を高める遺伝子と低める遺伝子とも10以上が見つかっており、それら遺伝子がコードするタンパク質の機能解析が待たれる。 感染症発症に関わる微生物側の因子についてもまだよく分かっていない。遺伝学を利用して微生物側の病原性因子を同定する試みもなされている。黒川健児氏(東京大学薬学部)は、黄色ブドウ球菌に無差別に突然変異を起こさせて、まず高温で増殖程度が変化する1000株ほどの菌を選んだ。次に、それらをカイコに感染させて病原性の程度を調べた。黒川氏の研究グループは、カイコを使うことによりこれまでの寒天培地上での微生物の増殖のみに頼った抗生物質の探索法からの脱却をはかっている。調べた変異菌の中には感染時のカイコの致死性が親株菌の場合と大きく異なるものが含まれており、変異遺伝子が病原性因子に関連するタンパク質をコードする可能性がある。今後の詳しい解析が期待される。 4. 3. 微生物側の戦略の研究微生物が自己の生存のために宿主の免疫を逃れたり、またその逆に利用する例が知られる。金沢大学医学系研究科の白土明子氏の研究グループは、細菌が免疫細胞の微生物感知受容体を使って殺傷を逃れることを見出した。黄色ブドウ球菌を貪食したマクロファージではTLR2に依存して活性酸素生産が低下した。これは、黄色ブドウ球菌がTLR2を介してMAPキナーゼのひとつであるJNKを活性化するためであることが分かり、微生物が宿主免疫応答を利用する新たな例となった。活性酸素減少は黄色ブドウ球菌の生存に有利だと思われるが、見方を変えると、宿主にとっても傷害を与える物質の生産を最小量に抑えるためであるとも解釈することができる。白土氏は先に紹介した黒川氏の樹立した変異菌を使ってTLR2に働きかける細菌側因子の同定に取り組んでおり、この研究が黄色ブドウ球菌感染での疾患発症の仕組みを解明することにつながる可能性がある。 マラリア原虫の感染で引き起こされる感染症は、毎年数百万人の人命を奪うたいへん深刻な疾患である。近年になって、マラリア原虫とともにその媒介昆虫であるハマダラカのゲノム構造が解明され、それに基づいて世界規模で新しい医療の開発が試みられている。鎮西康雄氏(三重大学医学部)はマラリア原虫と宿主との関係を規定する原虫側遺伝子の同定を行っている。遺伝子を変異させたマラリア原虫を使った研究を先駆的に行っており、本講演では宿主寄生性に必要な遺伝子の解析について発表した。蚊の吸血で宿主血液中に侵入したマラリア原虫は、肝臓にたどり着いて細胞内に入り込む。鎮西氏は、マラリア原虫の肝臓細胞への侵入と細胞内に留まる機構を調べ、それらの現象に必要な原虫遺伝子を見出した。増殖と分化を果たしたマラリア原虫は肝臓細胞を出て、今度は赤血球に入り込んで生殖性を獲得する変化を起こす。その後に赤血球を破壊して外に出ることがマラリア発症の実体であり、これまでマラリア原虫の肝臓での振る舞いはあまり調べられて来なかった。鎮西氏の研究で新たに同定された原虫遺伝子が標的となって新しい抗マラリア薬が開発されることが期待される。 5.感染症研究の今後の展開感染症は体内に侵入した微生物の増殖に伴って発症するため、原因が明白で単純な疾患だと思われがちである。しかし、もう少し考えを進めると根本的な部分が分かっていないことに気が付く。そして、感染症を予防・治療するための医療の開発が一筋縄ではないことが見えてくる。先に述べたように、侵入微生物の振るまいと免疫応答の詳しい解析が必要であることは確かだが、人類が感染症の危機から逃れるためには少々目先を変えた研究も必要であろう。 5. 1. 感染症発症の仕組み体内で微生物が増えたらなぜ病気になるのだろうか。自分の生存と増殖に都合がよいので、微生物は私たちの体内に侵入するはずである。そうすると微生物は、私たちが病気になって具合を悪くして死んでしまうと困る。おそらく、微生物は積極的には私たちに病気を起こそうとはしていないであろう。毒素を放出したりしない限り、微生物の存在自体が私たちにとって大きな害になるとは考えにくい。グラム陰性菌が表層に持つリポ多糖は“内毒素”として知られ、それだけを動物に投与しても量によって致死的となる。しかし、リポ多糖は一般的な毒物としての性質を有しておらず、宿主細胞の受容体に結合して免疫を誘導する細菌側の因子として知られる。これらの事実より、宿主の免疫応答がリポ多糖の“毒性”として表れているという解釈が可能である。これが正しければ、免疫反応は必ずしも宿主のプラスになるとは限らないことになる。そして、感染症の予防・治療には宿主の免疫を抑えることが必要だという所まで行き着く。さりとて、免疫をなくしてしまうと感染症の危険性が高まることは、後天性免疫不全症候群の患者を見れば明らかである。微生物の直接効果では説明できない感染症は宿主の過剰な免疫応答が原因となるという考え方は以前より有り、未だに議論の中にある。この考えをもう少し進めて、微生物感染に対する宿主側の防御システムを“微生物の除去”と“宿主の耐性”に分けて考えるべきだという主張がなされている。言うまでもなく、前者の役割を担うのが免疫である。侵入微生物を感知した免疫細胞は、それを除去するためにさまざまな反応を起こす。免疫反応は微生物を殺傷したり増殖阻害したりするために起こるが、同時に発熱や痛みを含めた不具合を宿主に生じさせる。その時に体を守ってくれるのが“宿主の耐性”機構である。こうして、侵入微生物の除去に十分な程度の免疫反応に体が耐え得れば感染症は防止されて健康が保たれる。しかし、耐性機構が不十分だと免疫反応の「副作用」に体が負け、不具合の症状が悪化して死に至ることもある。実際に、昆虫のショウジョウバエを使った研究では、“過剰な”免疫反応を抑制する仕組みを阻害すると、感染した微生物はあっという間に除去されるがほぼ同時に宿主が死んでしまう、という実験結果が報告されている。これは、“微生物の除去”と“宿主の耐性”を担う防御機構が別々に存在することを示唆する。これまでこのような視点から感染症が研究されることはほとんどなく、宿主の耐性を決める仕組みの一切は不明である。宿主耐性に関わる遺伝子の存在は容易に推察でき、それらの同定が最初の課題となろう。それには遺伝学的な解析が有利であり、嘉糠氏が行っているショウジョウバエの感染免疫関連遺伝子の網羅的解析により目的の遺伝子が見つかってくるかもしれない。 5. 2. 自然免疫と獲得免疫との関係自然免疫の定義は、“個体の出生後に再編成される遺伝子の働きを介さない免疫”である。再編成を受ける遺伝子は抗体や一部のリンパ球受容体をコードするものであり、免疫に“抗原に対する一対一認識”を賦与する役割を担う、と考えられている。この一対一認識が免疫学的記憶と合わせて、自然免疫には含まれない獲得免疫の特徴とされる。しかし、この考えでは説明できない事象が判明して、自然免疫と獲得免疫との関係を見直さなければならないのかもしれなくなってきている。 昆虫などが持つ「原始的な」免疫が精力的に研究され、私たち哺乳類にもそれと類似の免疫が備わっていることが確定し、自然免疫から原始的なという形容詞単語が外されて上記の定義が与えられた。そうすると、ショウジョウバエなどの昆虫は、“一対一認識”や“免疫記憶”を用いることなく侵入微生物と戦っていることになる。実際に、遺伝子再編成を受ける遺伝子と類似なものは昆虫には存在しない。しかし、自然免疫しか持たないはずの昆虫を含めたいくつかの生物において、“二度目に遭遇する微生物に対してはより高い耐性を示す”という実験結果が以前より報告されている。さらに最近になって、異なるスプライシングによって数万種類のタンパク質を生み出す遺伝子の存在が報告され、それらが免疫に関連した機能を持つことが示唆されている。これらの研究成果は、遺伝子再編成を伴わずに作られる“抗体類似”分子により自然免疫に一対一認識と免疫記憶の性質が与えられていることを想像させる。このように、免疫に関してこれまでの定義や理解では説明できない生命現象が分かってきて、免疫の考え方そのものを変える必要があるのかもしれない。 5. 3. 病原性微生物と共生微生物私たちの皮膚や粘膜にはさまざまな種類の微生物が住みついており、それらは常在微生物叢と呼ばれる。常在微生物叢は、出生の際に母親の産道や環境中にいる微生物が新生児に感染して形成される。これらの微生物と私たちとはギブ&テイクの関係を形成して共生しており、微生物側は私たちに感染抵抗性を与えることが分かっている。化学療法剤の過度な使用は、薬剤耐性微生物の出現のみならず、常在微生物叢の消失という弊害も伴うのである。常在微生物叢について今後に解析すべきことは、それらの微生物がどうやって宿主免疫から逃れて存在しているのか、そして叢を構成する微生物の種類の把握、の2点であろう。 常在性微生物も侵入微生物と同じく感染症を起こすことがある。それは宿主の免疫機能が低下した時であり、日和見感染と呼ばれている。日和見感染症の多くはすぐに直ってしまう場合が多く、常在性微生物に対しても免疫が働くことが分かる。つまり、常在性微生物は病原性を有しているとともに「異物」として宿主免疫に感知され、侵入微生物との間に大きな差はなさそうである。微生物の中にはさまざまなやり方で免疫を逃れるものがあるが、常在微生物叢を構成する微生物は積極的に免疫を逃れるようとはしていなのかもしれない。ウイルスなどの慢性感染のように、体内で増えて一定量に達すると免疫に感知されて量が減ることをくり返しているのだろうか。それにしては、常在微生物叢を構成する微生物は常に多く存在するように思われる。常在微生物が体内に存在し続ける仕組みを明らかにすることは、感染症の理解を深め、新しい原理に基づく感染症防止法の開発につながると期待される。 常在微生物叢を構成する微生物の同定はまったく行われていないのに等しい。それは、それらの微生物の大半は培養できないからである。歯周病細菌の半分程度、そして腸内細菌の9割以上が難培養性だと考えられている。つまり、それらの常在微生物叢を寒天培地に塗布しても、現れてくるコロニーは叢に存在する微生物のごく一部だけに由来するという訳である。さらに、環境中の微生物の99%程度が培養不能らしく、私たちを取り巻く微生物の大半はまだ人類の目に触れていないことになる。ある意味では、このような状況で「感染症を理解して対策を講じよう」とすることは無謀である。そこで、未知な微生物を同定し、種類を定めて分類しようとする試みが行われつつある。従来の“培養で増やして調べる”やり方は通用しないので、微生物の遺伝子から攻める方法がとられ、“メタゲノム”と呼ばれている。私たち人類だけでなく植物や昆虫に常在している微生物、通常の環境中に住む微生物、そして極限の環境中にいる微生物がこのような研究の対象とされている。どんなものが見つかるか、好奇心をもくすぐるプロジェクトが進行中である。 5. 4. 微生物による免疫の回避と利用前述したように、微生物はさまざまな手段を講じて宿主の免疫から逃れようとする。微生物としても、宿主体内に侵入してせっかく増殖できる環境を得たので、簡単には死ぬ訳にはゆかないと抵抗するのである。微生物が免疫を回避する仕組みの解明は日進月歩で行われつつある。このような微生物の振る舞いに対して宿主も逆襲する訳であり、ちょうど人類が開発した抗生物質への抵抗性を微生物が獲得する経緯に似ている。そうすると、微生物と宿主とは生存をかけて、太古の昔からそれぞれの武器を改良する進化を続けてきたと推測される。宿主の免疫機構、微生物の抵抗手段、そして宿主の逆襲、これらを担う遺伝子について進化の見地から解析を加えると、これまでとは異なる原理に基づいた感染症対策のアイデアが見えてくるかもしれない。
講演内容に関する参考文献
李氏の講演:
福井氏の講演:
佐々木氏の講演:
住本氏の講演: 嘉糠氏の講演:講演内容はすべて未発表
黒川氏の講演:黄色ブドウ球菌の遺伝子解析については未発表
白土氏の講演:黄色ブドウ球菌の遺伝子解析については未発表
鎮西氏の講演: |
| Copyright(c) 1996-2008 DOJINDO LABORATORIES,ALL Rights Reserved. |