 |
| トップページ > エイズから見た感染症研究の最前線 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイズから見た感染症研究の最前線
1.はじめに
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 1 |
日本で承認されている抗HIV-1薬(2007年11月現在) |
| 一般名 | 略号 | 商品名 | 承認時間(日本) |
|---|---|---|---|
| 核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI) | |||
| ジドブジン | AZTまたはZDV | レトロビル | 1987年11月 |
| ジダノシン | ddl | ヴァイデックス/ ヴァイデックスEC |
1992年7月/ 2001年3月 |
| ザルシタビン | ddc | ハイビット | 1996年4月 |
| ラミブジン | 3TC | エピビル | 1997年2月 |
| サニルブジン | d4T | ゼリット | 1997年7月 |
| ジドブジンと ラミブジンの合剤 |
AZT/3TC またはCBV |
コンビビル | 1999年6月 |
| アバカビル | ABC | ザイアジェン | 1999年9月 |
| テノホビル | TDF | ビリアード | 2004年4月 |
| アバカビルと ラミブジンの合剤 |
ABC/3TA またはEPZ |
エプジコム | 2005年1月 |
| エムトリシタビン | FTC | エムトリバ | 2005年4月 |
| テノホビルと エムトリシタビンの合剤 |
TDF/FTC またはTVD |
ツルバダ | 2005年4月 |
| 非核酸系逆転写酵素阻害剤(NNRTI) | |||
| ネビラピン | NVP | ビラミユーン | 1998年12月 |
| エファビレンツ | EFV | ストックリン | 1999年9月 |
| デラビルジン | DLV | レスクリプター | 2000年5月 |
| プロテアーゼ阻害剤(PI) | |||
| インジナビル | IDV | クリキシバン | 1997年4月 |
| サキナビル | SQV | インビラーゼ | 1997年9月 |
| ネルフィナビル | NFV | ビラセプト | 1998年3月 |
| リトナビル | RTV | ノービア | 1999年9月 |
| ロピナビルと リトナビルの合剤 |
LPV/r | カレトラ | 2000年12月 |
| アタザナビル | ATV | レイアタッツ | 2004年1月 |
| ホスアンプリナビル | FPV | レクシヴァ | 2005年1月 |
| ダルナビル | DRV | プリジスタ | 2007年11月(予定) |
1.2. 新規抗HIV薬のニーズの背景
「薬を飲まなかったら、命が無い。」これほど強いモチベーションを与える言葉はありません。その分、「もう大丈夫じゃないかな?」という気持ちが出てきたとき、あれほど一生懸命飲んでいた薬も、一回ぐらいならと飲み忘れを見逃すようになり、あっという間に服薬率が50〜60%位に低下していきます。なぜなら、今のHIV薬は、抗ウイルス効果に主眼がおかれ、「ある程度」の副作用は目をつぶっているため(「ある程度」とは、患者さん方が決めたのではなく、多分一回も飲んだことが無い、開発・販売・認可した側が決めたものと思われます)、HIV感染による諸症状がなくなると、差し引き薬の副作用だけが残ります。つまり、飲むたびに、お腹が緩くなるし、意味もなくイライラしたり、夜中に変な夢を見たりします。また、長い間飲み続けると体型が変わってきますし、糖尿病や心臓病になる人も増えてきます。人間とは弱いもので、そうなるとますます100%飲み続けることは困難になっていきます。もちろん、主治医や、スタッフが服薬の必要性や副作用の緩和の方法等を根気よく説明し続けることで、モチベーションを維持し良好なコントロールができている患者さんも大勢おられます。ただ、なかなか全ての施設で全ての患者さんに行うことは困難なのです。
一方、HIVの本当の恐ろしさは、そのしつこいまでの感染維持能力にあると言っても過言ではありません。少しでも薬剤の濃度が低下すると、すぐさまウイルスの増殖は再開されます。しかも、悪いことに中途半端に薬が血中に存在するために薬剤耐性変異を持ったウイルスが出てきたりします。実際、欧米では初回治療の半数以上が、副作用と耐性発現のために、一年以内に治療のレジュメを変更しているというデータもあります。こうなると、20種類以上薬があるといっても、実は大きく分けて逆転写酵素阻害剤とプロテアーゼ阻害剤の2つしかないので、一度耐性が出ると、交叉耐性の関係で使える組み合わせが極端に減少してしまいます。すると現場の関係者は「耐性に効く薬が必要だ。」とか、「飲みやすくて、気分が悪くならないものはないのか。」と、勝手なことを言いだします。このように、HIVというウイルスの性質および人間の本質上、常に新しい薬剤の要求は続いていくのです。
今回、現在開発が進行中もしくは臨床使用が近いHIV-1薬を中心に紹介していきたいと思います。
2.新規HIV薬剤の開発
2.1. 侵入阻害剤
このシリーズの1回目と2回目(News No.121,122)に、詳しく説明されていますように、HIVはCD4とケモカイン受容体(CXCR4またはCCR5)の2種類の分子と結合することでTリンパ球に侵入することが分かっています。つまり、この過程を阻止すると感染が成立しなくなりますので、薬剤のターゲットとしては格好の場所といえます。この結合阻害には、ウイルス側をターゲットにするものと、受容体側をターゲットとするものの2通りが考えられます。
前者の代表である『PRO-542』は、合成したCD4分子にIgGを付けたもので、本物の細胞表面のCD4分子に付着できないようにして、感染を阻害します。phase まで終了し、そこそこの効果もあり、安全性にも問題ないのですが、現在開発が中断しています。どうやら開発している会社が、他の薬剤の方を一押しにして開発しているためらしいです(後述する『PRO-140』)。(財)化学及血清療法研究所(化血研)と熊本大学エイズ学研究センター病態制御分野(松下修三教授)では、HIV-1のgp120の三番目の可変領域(V3 loop)に対する治療用中和単クローン抗体『KD-247』を開発中です。日本や米国で多いsubtype Bのウイルスで保存されている、V3 loopのtip部分の-GPGR-配列を認識し中和します。抗体のため、血中半減期が長く、月に1-2回の注射で十分効果が持続します。現在米国でphase
まで終了し、そこそこの効果もあり、安全性にも問題ないのですが、現在開発が中断しています。どうやら開発している会社が、他の薬剤の方を一押しにして開発しているためらしいです(後述する『PRO-140』)。(財)化学及血清療法研究所(化血研)と熊本大学エイズ学研究センター病態制御分野(松下修三教授)では、HIV-1のgp120の三番目の可変領域(V3 loop)に対する治療用中和単クローン抗体『KD-247』を開発中です。日本や米国で多いsubtype Bのウイルスで保存されている、V3 loopのtip部分の-GPGR-配列を認識し中和します。抗体のため、血中半減期が長く、月に1-2回の注射で十分効果が持続します。現在米国でphase bが進行中です。
bが進行中です。
一方、後者の宿主側の受容体をターゲットとする薬剤は、抗エイズ薬の中では異色の薬剤群です。なぜなら、これまでHIV薬開発のコンセプトは、ウイルス特異的な酵素や構造蛋白を攻撃するものだったからです。逆転写酵素しかり、プロテアーゼしかり、インテクラーゼやエンベロープ蛋白(gp120、gp41)しかりです。ところが、CCR5やCXCR4、CD4というのは細胞側のものなので、阻害剤の開発には二の足を踏んできました。宿主側の分子をブロックすることで、どのような副作用が発現するか分からなかったからです。それでも、現場の要請と圧倒的な抗ウイルス効果の強さや、作用点が違うことなどから、これらの阻害剤の開発が予想外に速いスピードで進んできました。CCR5阻害剤の『Celzentry (Maraviroc; UK-427,857)』は2007年の8月にアメリカFDAに認可され、近々日本でも使用可能になりますし、『Vicriviroc (SCH-D)』もphase
(Maraviroc; UK-427,857)』は2007年の8月にアメリカFDAに認可され、近々日本でも使用可能になりますし、『Vicriviroc (SCH-D)』もphase が進行中です。CCR5阻害剤は、R5ウイルスにしか効かないため、投与前にウイルスのフェノタイプ検査が必要であり、検査時に見つからなかったX4ウイルスが増えてくる危険性もありますが、少なくとも既存の薬剤に高度耐性になったウイルスに対してもR5ウイルスである限りにおいて、単剤でもウイルス量を1/100にまで減らすことができます。我々の研究室では、CCR5阻害剤と上述した中和単クローン抗体KD−247が強い相乗効果を示すことを試験管内実験で確認しています。このように、これらの薬剤とその他の抗ウイルス薬の組み合わせで、思わぬ相乗効果が生まれる可能性も期待されています。R5だけでなくX4ウイルスもカバーする必要があるため、CXCR4阻害剤である『AMD070(AMD11070)』も現在phase
が進行中です。CCR5阻害剤は、R5ウイルスにしか効かないため、投与前にウイルスのフェノタイプ検査が必要であり、検査時に見つからなかったX4ウイルスが増えてくる危険性もありますが、少なくとも既存の薬剤に高度耐性になったウイルスに対してもR5ウイルスである限りにおいて、単剤でもウイルス量を1/100にまで減らすことができます。我々の研究室では、CCR5阻害剤と上述した中和単クローン抗体KD−247が強い相乗効果を示すことを試験管内実験で確認しています。このように、これらの薬剤とその他の抗ウイルス薬の組み合わせで、思わぬ相乗効果が生まれる可能性も期待されています。R5だけでなくX4ウイルスもカバーする必要があるため、CXCR4阻害剤である『AMD070(AMD11070)』も現在phase /
/ が行われています。その他に、『TNX-355』という CD4分子に対する治療用単クローン抗体があります。静脈注射で投与する必要があるのですが、一回打つと2-3週間もつので、月2回投与ですみます。アメリカでphase
が行われています。その他に、『TNX-355』という CD4分子に対する治療用単クローン抗体があります。静脈注射で投与する必要があるのですが、一回打つと2-3週間もつので、月2回投与ですみます。アメリカでphase 試験まで終了しています。CCR5に対しては直接結合する『PRO140』という単クローン抗体も、phase
試験まで終了しています。CCR5に対しては直接結合する『PRO140』という単クローン抗体も、phase が終了しています。半減期が2週間と長く、他の薬剤との相乗効果も見られており、FDAからファーストトラック(有望なので優先して審査するというお墨付き)の指名を受けており、予想より早く臨床の場にデビューするかもしれません。
が終了しています。半減期が2週間と長く、他の薬剤との相乗効果も見られており、FDAからファーストトラック(有望なので優先して審査するというお墨付き)の指名を受けており、予想より早く臨床の場にデビューするかもしれません。
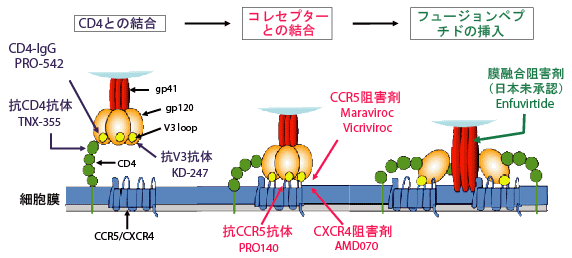
Fig.1 HIV-1 侵入阻害剤の作用部位
2.2. インテグラーゼ阻害剤
インテグラーゼの主な働きは、逆転写後のプロウイルスDNAの3'末端に存在するGとTを切断するプロセシング反応と、ウイルスゲノムに組み込む結合反応です。また、ヒトには存在しないHIV特異的な酵素で、逆転写酵素やプロテアーゼと同様にHIVの複製において重要な酵素です。そのため、抗HIV薬の有望なターゲットとして以前より開発が続けられてきました。『Isentress (Raltegravir; MK-0518)』は、つい最近(2007年10月)米国FDAに認可されたばかりのインテクラーゼ阻害剤です。HIV未治療の患者においてビリアード
(Raltegravir; MK-0518)』は、つい最近(2007年10月)米国FDAに認可されたばかりのインテクラーゼ阻害剤です。HIV未治療の患者においてビリアード (テノホビル)とエピビル
(テノホビル)とエピビル (ラミブジン)とRaltegravir、もしくはコントロール群としてストックリン
(ラミブジン)とRaltegravir、もしくはコントロール群としてストックリン (エファビレンツ)を併用して24週間試験を行ったところ、Raltegravir投与群ではHIVウイルス量が50コピー/mlに減少した患者の割合が85%〜95%で、コントロール群(92%)とほぼ同等の結果でした。ただ、HIVウイルス量の低下速度は、Raltegravir併用群の方が明らかに速かったのです。この薬剤は、肝臓のCYP3A4の代謝を受けないため、CYP3A4阻害効果を持つノービア
(エファビレンツ)を併用して24週間試験を行ったところ、Raltegravir投与群ではHIVウイルス量が50コピー/mlに減少した患者の割合が85%〜95%で、コントロール群(92%)とほぼ同等の結果でした。ただ、HIVウイルス量の低下速度は、Raltegravir併用群の方が明らかに速かったのです。この薬剤は、肝臓のCYP3A4の代謝を受けないため、CYP3A4阻害効果を持つノービア (リトナビル)のブーストを必要としません。よって、併用薬剤を一剤減らせます。もう一つのインテグラーゼ阻害剤の『Elvitegravir (GS9137/JTK-303)』もphase
(リトナビル)のブーストを必要としません。よって、併用薬剤を一剤減らせます。もう一つのインテグラーゼ阻害剤の『Elvitegravir (GS9137/JTK-303)』もphase まで進んでいます。Elvitegravirはキノロン系抗菌剤を修飾した構造を持ち、マグネシウムイオンと結合することで、インテグラーゼの働きを抑えます。また、試験管内において多剤耐性HIV-1 ウイルスに対しても抗ウイルス活性が示され、他の抗レトロウイルス薬との相乗効果も確認されています。ただし、Elvitegravirは、CYP3A4の代謝を受けるので、治療域に到達させるために低用量のノービア
まで進んでいます。Elvitegravirはキノロン系抗菌剤を修飾した構造を持ち、マグネシウムイオンと結合することで、インテグラーゼの働きを抑えます。また、試験管内において多剤耐性HIV-1 ウイルスに対しても抗ウイルス活性が示され、他の抗レトロウイルス薬との相乗効果も確認されています。ただし、Elvitegravirは、CYP3A4の代謝を受けるので、治療域に到達させるために低用量のノービア ブーストとして用いる必要があります。インテグラーゼ阻害剤の不安な点は、長期使用による副作用が予測できないことと、一部交叉耐性が認められており、どちらか一方の使用で耐性が出たとき、他方は使えなくなる危険性があることです。それでも、切れ味鋭いウイルス抑制効果に大きな期待がかかっています。
ブーストとして用いる必要があります。インテグラーゼ阻害剤の不安な点は、長期使用による副作用が予測できないことと、一部交叉耐性が認められており、どちらか一方の使用で耐性が出たとき、他方は使えなくなる危険性があることです。それでも、切れ味鋭いウイルス抑制効果に大きな期待がかかっています。
2.3. 非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)
一日一回投与の中心的な薬剤として、プロテアーゼ阻害剤とともにHAARTの4番打者の地位を長らく務めてきました。しかし、近年耐性ウイルスが問題となってきており、初感染の患者からもその耐性変異が認められるケースが増えてきています。また、中枢神経系の副作用により、中断を余儀なくされる症例も多いのです。そのため、このクラスの新規薬剤で求められることは、既存の薬剤と交叉耐性を示さないということと、中枢神経系の副作用の軽減です。言うのは簡単ですが、このハードルはなかなか高かったらしく、2000年にレスクリプター (デラビルジン)が認可されて以来、『Etravirine (TMC125)』は、久々にphase
(デラビルジン)が認可されて以来、『Etravirine (TMC125)』は、久々にphase まで進んだNNRTIで、FDAの認可も近いと考えられています。この薬剤の最も優れたところは、これまでのNNRTIに完全に耐性になったウイルスにも効果があるという点です。つまり、耐性のプロフィールがかなり違っているのです。ただし、このクラスの薬剤で以前から指摘されていたプロテアーゼ阻害剤との併用で血中濃度が低下するという問題点は引き継がれているようなので、両者の併用には注意が必要になりそうです。このEtravirineのすぐ後を追いかけるように『Rilpivirene (TMC278)』が現在phase
まで進んだNNRTIで、FDAの認可も近いと考えられています。この薬剤の最も優れたところは、これまでのNNRTIに完全に耐性になったウイルスにも効果があるという点です。つまり、耐性のプロフィールがかなり違っているのです。ただし、このクラスの薬剤で以前から指摘されていたプロテアーゼ阻害剤との併用で血中濃度が低下するという問題点は引き継がれているようなので、両者の併用には注意が必要になりそうです。このEtravirineのすぐ後を追いかけるように『Rilpivirene (TMC278)』が現在phase まで進んできています。この薬剤は、これまでのNNRTIがたった一つの耐性変異で効かなくなっていたのに比べ、これまでに知られている変異が8つ以上集まって初めて効かなくなります。具体的には、L100I/K103NやK103N/Y181Cなどを持った高度NNRTI耐性ウイルスにも充分効果があるということです。また、一日25mgと75mgと150mg投与群で48週後の血中ウイルスの測定感度以下(<50コピー/ml)になった人の割合を比較すると、驚いたことに全ての群で約80%と、ほとんど変わらないぐらいの強い抗ウイルス効果を示しました。そして、これは同時に比べた一日600mg投与のエファビレンツと同等の数字でした。CD4数の上昇が75mg群で最も良かったので、今後は75mg/日で臨床治験がすすめられることになっています。投与濃度が非常に低いので、中枢神経症状がエファビレンツに比べると非常に少ないという利点があります。ただ、血中半減期が非常に長いので、蓄積効果による副作用発現がどうなるかを見守っていかなければいけません。Phase
まで進んできています。この薬剤は、これまでのNNRTIがたった一つの耐性変異で効かなくなっていたのに比べ、これまでに知られている変異が8つ以上集まって初めて効かなくなります。具体的には、L100I/K103NやK103N/Y181Cなどを持った高度NNRTI耐性ウイルスにも充分効果があるということです。また、一日25mgと75mgと150mg投与群で48週後の血中ウイルスの測定感度以下(<50コピー/ml)になった人の割合を比較すると、驚いたことに全ての群で約80%と、ほとんど変わらないぐらいの強い抗ウイルス効果を示しました。そして、これは同時に比べた一日600mg投与のエファビレンツと同等の数字でした。CD4数の上昇が75mg群で最も良かったので、今後は75mg/日で臨床治験がすすめられることになっています。投与濃度が非常に低いので、中枢神経症状がエファビレンツに比べると非常に少ないという利点があります。ただ、血中半減期が非常に長いので、蓄積効果による副作用発現がどうなるかを見守っていかなければいけません。Phase の結果が最も楽しみな薬剤の一つです。
の結果が最も楽しみな薬剤の一つです。
2.4. ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤(NRTI)
HIV-1の治療の歴史は、NRTIのレトロビル (ジドブジン)から始まりました。それ以降、このクラスの薬剤は、HAARTにおける渋いバイプレーヤーとして、目立たないながらも重要な役割を担ってきました。歴史が長い分耐性の蓄積も多く、NNRTIと同様に耐性プロフィールの異なる新薬の登場が切望されています。『Apricitabine (AVX754/SPD754)』は、これまでのNNRTIに強い耐性を持つウイルスに対して活性を示す、新しいシチジンアナログです。現在phase
(ジドブジン)から始まりました。それ以降、このクラスの薬剤は、HAARTにおける渋いバイプレーヤーとして、目立たないながらも重要な役割を担ってきました。歴史が長い分耐性の蓄積も多く、NNRTIと同様に耐性プロフィールの異なる新薬の登場が切望されています。『Apricitabine (AVX754/SPD754)』は、これまでのNNRTIに強い耐性を持つウイルスに対して活性を示す、新しいシチジンアナログです。現在phase bに入っており、エピビル
bに入っており、エピビル (ラミブジン)で治療が失敗したM184V変異を持つHIV感染患者に対して試験が行われています。本剤は、FDAからファーストトラックとして指定を受けています。『Racivir』は、HIV-1およびB型肝炎ウイルス(HBV)の両方に対する抗ウイルス活性を有しています。現在HIV-1の治療薬としてphase
(ラミブジン)で治療が失敗したM184V変異を持つHIV感染患者に対して試験が行われています。本剤は、FDAからファーストトラックとして指定を受けています。『Racivir』は、HIV-1およびB型肝炎ウイルス(HBV)の両方に対する抗ウイルス活性を有しています。現在HIV-1の治療薬としてphase /
/ が行われています。『Elvucitabine (L-Fd4C)』もレトロビル
が行われています。『Elvucitabine (L-Fd4C)』もレトロビル やエピビル
やエピビル の耐性ウイルスにも効果があり、HBVにも有効です。現在phase
の耐性ウイルスにも効果があり、HBVにも有効です。現在phase が進行中です。珍しいNRTIとして『KP-1461 (KP-1212)』があります。この薬は、他のNRTIと違い、チェーンターミネーターとして抗ウイルス効果を発揮するのではなく、ウイルスのゲノムに変異を蓄積していって、ウイルスを増えられなくしていきます。現在phase
が進行中です。珍しいNRTIとして『KP-1461 (KP-1212)』があります。この薬は、他のNRTIと違い、チェーンターミネーターとして抗ウイルス効果を発揮するのではなく、ウイルスのゲノムに変異を蓄積していって、ウイルスを増えられなくしていきます。現在phase が行われています。
が行われています。
2.5. マイクロビサイド
マイクロビサイドとは、膣や肛門の中に入れておいて、HIVの感染を阻止するような物質(錠剤・ゼリー状・シート状・スポンジ状のもの)のことをいいます。現在、FDAのInvestigational drugsに指定されるもので最も数が多いのはこのマイクロビサイドです。これらは、予防という側面で開発されている唯一の薬剤といっていいでしょう。要時使用という使い方が可能ということは、経済的にも副作用の面でも大きな利点があります。ただし、ハイリスク群で比較したとき、使用した方の感染率がかえって高かったという結果も出ており、今後より慎重な研究が必要です。
3.終わりに
ここでご紹介できなかった開発中の薬剤は、まだまだたくさんあります。また、ワクチンの開発も道半ばではありますけれど、確実に前進していっています(と信じています)。新規薬剤の開発と耐性ウイルスの出現は、一見イタチごっこのように見えます。でも、明らかに、イタチ(ウイルス)の足は目に見えて遅くなり、隠れたまま屋根裏から出てこなくなり、その時間も長くなっています。あと少しで、あきらめて出て行ってくれるかもしれません。そのためには、研究者はより効果的な薬剤を開発し、臨床医は服薬の重要性を説き、家主(患者さん)は巣穴からイタチ(ウイルス)が顔を出さないか辛抱強く見張っていなければならないのです。手負いのイタチ(耐性ウイルス)を逃がすと、次に捕まえるのが大変になりますので、くれぐれもご用心ください。
| 著者紹介 | |
 |
氏名:吉村 和久 (よしむら かずひさ) 所属:熊本大学エイズ学研究センター 病態制御分野 住所:熊本市本荘2-2-1 TEL:096-373-6536 研究テーマ:HIVの中和抗体からの逃避機構の解明 |
| Copyright(c) 1996-2007 DOJINDO LABORATORIES,ALL Rights Reserved. |