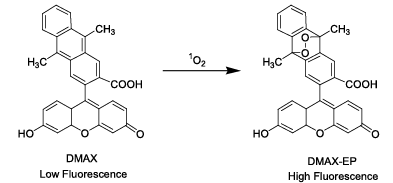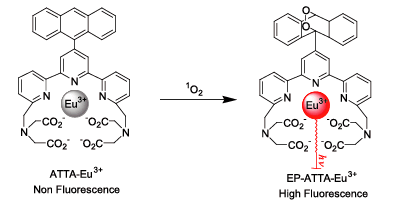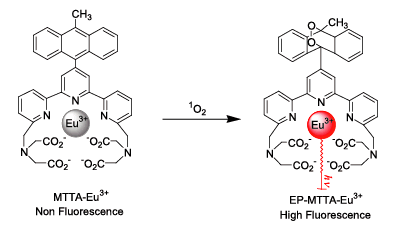|
| トップページ > 一重項酸素の特異的検出 |
 |
||||||
一重項酸素の特異的検出株式会社同仁化学研究所 永田 貴裕 活性酸素は、体内の細胞を破壊し、癌、心筋梗塞、脳血栓の原因物質として注目を集めている。呼吸により体内へ取り込まれた酸素の約3%が活性酸素になると言われており、この他にも外的要因として、ストレス、紫外線、アルコール、電磁波、排気ガスなどによっても体内で活性酸素が大量に発生することが明らかとなっている。また、これらの外的要因の殆どは、現代社会特有の環境によるものであり、現代人にとって活性酸素は、大きな病的要因の一つとして注目されている。 活性酸素種(Reactive Oxygen Species; ROS)には、スーパーオキシド、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、過酸化水素があるが、これら特定の活性酸素種の特異的検出に関しては問題がある。なぜなら活性酸素の反応は多様であり、それぞれの活性酸素に独特の反応特性や基質特異性を持つと同時に共通の反応性を示すことも多く、個々の活性酸素を特異的に検出する試薬の設計は非常に難しい。そのため、反応種の特定には検出試薬を活性酸素阻害剤、例えばスーパーオキサイドディスムターゼ(superoxide dismutase:SOD)やカタラーゼなどの酵素と共に使用した間接検出法が一般的に使用されている。 これら活性酸素は、生体内で微量に生成し、かつ寿命が短いため、直接的検出を行うには、高感度かつ高い反応性を有する検出試薬が求められる。活性酸素の中で紫外線により生じ、特に酸化力が強い一重項酸素(1O2)は、皮膚傷害や老化の加速を引き起こすと言われている。今回はこの一重項酸素(1O2)を特異的に検出できるプローブについて紹介する。
1O2蛍光プローブの代表例として挙げられるDCFH1)は、ROS間の種特異性に乏しく、また励起光を照射するだけで蛍光が増大してしまうなど、多くの問題点を抱えている。Naganoらは、ene反応によるアントラセン類の電子密度変化を利用した1O2特異的な検出蛍光プローブDMAX(Fig.1)を開発した2)。DMAXの一重項酸素に対する反応速度は、2.5×107 M-1s-1であり、寿命の短い1O2を測定するのに適したプローブであるといえる。また、他のROSに対しても殆ど反応性を示さないことからも、特異的1O2検出試薬であるといえる。
一方、Bo Songらにより開発されたATTA-Eu3+(Fig.2)は、ユウロピウム錯体を構造中にもつ1O2特異的なプローブである3)。検出感度は、2.8nMと非常に高く、反応速度は、2.5×109M-1s-1となった。さらにBo Songらは、ATTA構造にメチル基をつけたMTTA-Eu3+(Fig.3)を合成したところ、検出感度は、3.8nMと劣るが反応速度は約18倍増加した4)。これは、寿命の短い一重項酸素を測定する上で非常に優位な結果となり、高感度な1O2検出が期待される。また、in vitroでの実験においても、細胞内1O2濃度依存的に蛍光強度が増加することが確認された。
これまで、寿命が短く測定が困難とされてきた活性酸素種であるが、有用な検出プローブの開発により、活性酸素により引き起こされる病気の診断、さらには酸化ストレスに対する薬剤開発への利用が期待される。 参考文献1) LeBel, C. P., Ishchiropoulos, H. & Bondy, Chem. Res. Toxicol., 1992, 5, 227-231. |
| Copyright(c) 1996-2007 DOJINDO LABORATORIES,ALL Rights Reserved. |