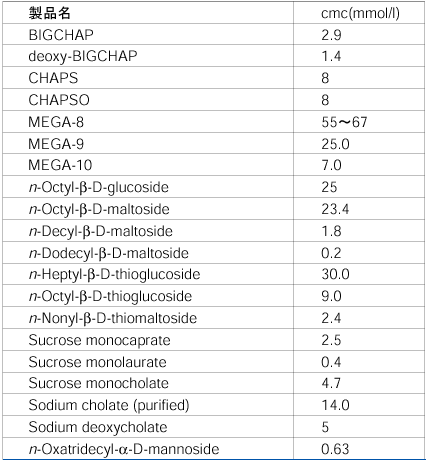
Q&A
界面活性剤とは、その物質を加えることにより液体の界面の張力を著しく低下させる物質のことです。この性質を生化学実験に使用する場合と洗浄のために洗剤として使用する場合があります。
ここでは、生化学実験においてタンパク質可溶化剤として使用する際に疑問としてあげられる内容について記載しております。
Q1 タンパク質可溶化剤としての界面活性剤の分類を教えてください。
A1 界面活性剤は親水基と疎水基を合わせもつ分子です。親水基と疎水基の種類によって分類されます。親水基はイオン性、両イオン性、非イオン性の三種類に大きく分けられます。非イオン性はポリアルコール系とポリエーテル系があります。
Q2 種類が多く、どれを使えばよいのか判りません。選択基準を教えてください。
A2 目的とするタンパク質が可溶化でき、余分なタンパク質を可溶化しないというのが第一の条件になります。さらに、目的タンパク質を失活させないこと、タンパク質を取り出した後の分離が容易なことが重要な要素となります。その他には毒性がないこと、安定であること、安価であることなどが要求されます。
オールマイティにタンパク質可溶化剤として使用できる界面活性剤はありません。可溶化しようとするタンパク質と界面活性剤の相性も考慮して選択していただくことになります。
どれがよいか検討する際に小社では、5種類の界面活性剤を小容量にしてセットとしたDetergent Screening Setを2種類用意しております。一般的に使用される first choiceのセットと、タンパク質の結晶化を目的としたfor crystallizationのセットをお試し下さい。
Q3 cmc(臨界ミセル濃度)はタンパク質可溶化にどのように関係するのですか。
界面活性剤はcmc以上の濃度でないとミセルを形成しません。
その濃度以上でないとタンパク質の可溶化も出来ません。タンパク質を可溶化する場合、最終濃度がcmc以上となるように調製する必要があります。
一方、タンパク質を可溶化した溶液からこの界面活性剤を除去するときにもcmcは重要となります。透析を例として説明します。ミセルは界面活性剤の集合体ですが、ミセルを形成することで一つの大きな分子として振る舞います。ミセルを形成している場合、ミセルは透析膜を通過出来ません。よって、cmcが比較的大きい分子ほど、モノマーの状態の比率が高くなる傾向がありますので、透析により簡単に除去できます。cmc以下に希釈すれば透析はさらに容易になるので、cmcが高いほど低い希釈率で透析ができます。
Q4 cmc(臨界ミセル濃度)を比較してみたい。
A4
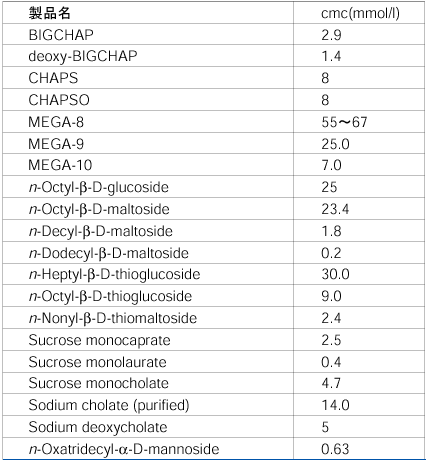
※ここに示すcmcは文献からの引用です。測定方法、温度条件等により数値は変わりますことをご承知下さい。
Q5 n-Octyl-β-D-glucosideと n-Octyl-β-D-thioglucosideでは性質上どのような違いがありますか。
A5 n-Octyl-β-D-glucosideはタンパク質可溶化剤としては良いものですが、開発された当初は製法上、それまでの界面活性剤に比べ非常に高価なものでした。そこで、安価に製造できるものとして開発されたのが、n-Octyl-β-D-thioglucoside です。現在はn-Octyl-β-D-glucosideも製法が改善され、以前より価格も安くなっております。
性質の違いとして、n-Octyl- b-D-glucosideはアセタール構造であるため、加水分解されることがあります。それに対してn-Octyl-β-D-thioglucosideの場合、アセタールの酸素が硫黄原子に置き換わっているため加水分解され難いといった性質があります。
濃度が微妙に変化することにより、実験結果に影響を与えることがあり、また分解物が悪影響を与えることも十分考えられます。
n-Octyl-β-D-glucosideは水溶液の状態では安定性は高くありません。用事調整にて使用いただくのが望ましいでしょう。(その他A6もご覧下さい)。
Q6 n-Octyl-β-D-glucosideはβ-グルコシダーゼで加水分解されますか。
A6 加水分解されます。グルコシダーゼが入っているような試料を取り扱う場合には、注意が必要です。n-Octyl- b-D-
thioglucosideに関してはβ-グルコシダーゼでは分解されません。
Q7 n-Octyl-β-D-thioglucosideのcmcは n-Octyl-β-D-glucosideの代替として使用できますか。
A7 両者は類似した性能を有しており、可溶性に多少の違いはありますが、代替品として使用可能です。
ただし、n-Octyl-β-D-thioglucoside のcmcは9 mmol/lとn-Octyl-β-D-glucoside(cmc 25 mmol/l)に比べ小さいので、cmcや膜タンパク質の可溶化に用いられる有効濃度を考えるとn-Heptyl-β-D-thioglucoside(cmc 30 mmol/l)の方が使いやすいかもしれません。
参考文献
土屋友房、島本整、斉藤節生、蛋白質、核酸、酵素、 30 (9), 52 (1985).
Q8 長鎖アルキル基とステロイド骨格基ではどのような違いがありますか。
A8 ステロイド骨格を持つ界面活性剤はコール酸系統が一般的です。この界面活性剤は数分子で会合してミセルを形成するため、ミセルサイズも小さく、透析により除去され易いという特徴があります。
長鎖アルキル基との組み合わせでは、親水基として糖を結合したものがタンパク質可溶化剤として用いられるものが多くあります。
Q9 糖鎖を親水基にした可溶化剤の特長を教えてください。
A9 以下のような特長があります。
・可溶化したタンパク質をイオン交換クロマトグラフィーで精製できる。
・マイルドな溶解作用を持つので変性しやすいタンパク質に適している。
・多糖類を結合している膜タンパク質の可溶化や精製に良く用いられる。
Q10 n-Octyl-β-D-glucosideで可溶化したタンパク質をそのまま生体へ投与可能ですか。
A10 小社製品は試験・研究用です。生体成分(細胞や大腸菌など)のタンパク質の可溶化には使用されておりますが、それを生体に直接投与したデータは持ちあわせておりません。従いまして、投与の可否についてはわかりません。