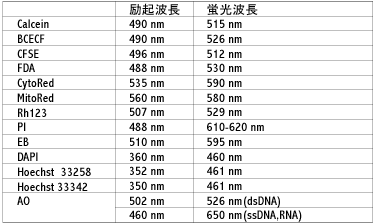
Q&A
その他、フローサイトメトリーやプレートリーダーによる細胞数の計測などへも利用されています。
Q1 それぞれの色素の蛍光特性を教えてください。
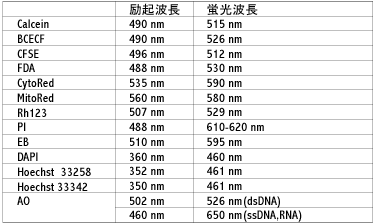
Q2 生細胞染色色素の特徴は?
A2 細胞機能への影響が一番少ないといわれているのは
「Calcein-AM」です。(Q7参照)
「FDA」は一番古くから知られている色素ですが、細胞から の漏出が早いといわれています。
「CFSE」は細胞内に導入後、細胞質内(細胞膜)のアミノ 基と結合するため他の色素に比べ細胞外への漏出が少ないと いわれています。
「BCECF-AM」は、元々細胞内のpHを測定する試薬として 利用されていたものであり、生細胞を染色する色素としても 利用されます。
「CytoRed」は、小社にて開発した化合物で、「Calcein-AM」 よりも高い蛍光強度を示します。
Q3 核染色に使用される色素の違いは何ですか?
A3 蛍光波長以外に違いとしてあげられるものとしては以下の点 があります。
「EB」塩基特異性はなく、全DNA、RNAに結合します。
「PI」「EB」と同様に塩基特異性はありませんが、インター カレーションした時の蛍光強度が「EB」より高いため、よ り広く使用される色素です。
「DAPI」2重鎖の副溝(minor groove)と結合、アデニン-チミジンクラスターに高い結合性を持っています。
「AO」2重鎖にインターカレーションしたときと、単鎖のリ ン酸に結合したときでは蛍光波長が異なることを利用して、 2重鎖と単鎖を区別して検出できます。生細胞の細胞膜を透 過します。
「Hoechst 33342」DNAのアデニン-チミジン部に特異的に結合します。生細胞の膜を透過し、生細胞のDNAを染色 できる色素です。
Q4 「MitoRed」と「Rh123」はなぜミトコンドリア染色用なので すか?
A4 「MitoRed」、「Rh123」はともに「Rhodamine」と呼ばれ る構造を骨格としています。この「Rhodamine」は細胞の 中に入ると、ミトコンドリアに集積していく特性があるため ミトコンドリア染色色素として使用されます。もちろん多量 に細胞内に導入すると他の部分も染色されてしまいますの で、濃度をご検討の上適量をご使用ください。
Q5 2種類の色素を同時に使用することはできますか?
A5 可能です。しかし波長が重なる色素を同時に使用することは できません。
使用例としては、「Calcein-AM」で生細胞の細胞質を染色、 「PI」で死細胞の核を染色する「Double Staining Kit」があります。(小社カタログ、ホームページをご参照ください。)
また、「Hoechst」で生細胞の核を染色、「PI」で死細胞の核 を染色する方法もあります。
Q6 使用方法(濃度や時間)を教えてください。
A6 ホームページの「Q&A」に各試薬の使用例を、一部掲載し ていますのでご参照ください。
(http://dominoweb.dojindo.co.jp/FAQkoukai.nsf/ webhome/index)。
ただし、試料により最適濃度は異なります。濃度が高すぎる と余分なものまで染まる場合があります。
状況に応じ、最適な濃度や時間をご検討ください。
Q7 色素の細胞毒性について報告されている論文はありますか?
A7 「Calcein-AM」、「BCFECF-AM」、「CFDA」、「CFSE」が 細胞に与える障害活性を比較した論文がありますのでご参照 ください。
L. S. D. Clerck, et al.,J.Immunol. Methods, 172,115(1994).
Q8 細菌の染色をしたいのですが、どの色素を使えば可能でしょ うか?
A8 細菌は「細胞壁」を持つため、その細胞壁を通過できない色 素が多くあります。例えば「Calcein-AM」や「BCECF-AM」 は細胞膜は通過できますが、細胞壁は通過できません。
細菌の染色目的に使用できる色素としては、例えば「AO(ア クリジンオレンジ)」がマラリア原虫の染色として使われて います。死菌ならば「PI」「EB」「DAPI」なども使用できま す。
生菌染色は「FDA」の報告があります。
Appl. Microbiol. Biotechnol., 38,268(1992).他