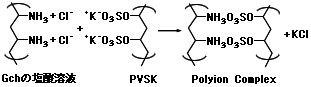新製品
【はじめに】
コロイド滴定法の最初の発表は戦後の困難な時代に第4回膠質化学討論会(1946年10月)においてなされている。開発の経緯が創案者である寺山宏教授(東京大・理)によって、ぶんせき誌の「創案と開発」欄に詳しく紹介されおり、一読に値する1)。発表の当初はタンパク質やタンニンのような高分子電解質が簡単に定量できるというので大きな反響を呼んだが、当時の試薬性能の不十分さのために、広く普及するに至らなかった。
その後、九州大学農学部の千手諒一教授によって、重合度の高いポリカチオンを使えば、再現性のある結果が得られることが明らかにされ、再び注目される事となった。この滴定法は天然に存在する多くのコロイド物質が対象となるため、農学方面に活発な応用がなされた2)。
【原理】
コロイド滴定の原理はポリカチオンとポリアニオンがその強いクーロン引力で、瞬時にポリイオンコンプレクスを形成することに基づいている。
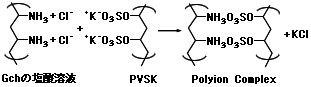
滴定の終点検出には吸着指示薬のメタクロマジー現象が利用されている。標準ポリカチオンとしてはグリコールキトサン(Gch)、標準ポリアニオンとしてはポリビニル硫酸カリウム(PVSK)が使用された。1/400NのGch溶液を、1/400NのPVSK標準液で滴定すると、徐々に白濁し、滴定の終点では指示薬として加えたトルイジンブルー(TB)が青色から赤紫色に変色する。TBはカチオン色素であり、液性がカチオンコロイドである限り、元の青色を保っているが、滴定終点でPVSKが一滴でも過剰になると、アニオンコロイドに吸着され赤紫色に鋭敏に変色する。Gchが酸性側でのみカチオンコロイドとして働くので、アミノ基をヨウ化メチルで四級化し、広いpH領域でカチオンとして働くようにしたメチルグリコールキトサン(MGch)を千手教授らはポリカチオンの標準品として推奨している。しかし、MGch、Gchいずれも蟹の甲羅から得られる天然高分子であり、純粋な一定重合度のものが得られ難いのと、四級化度が定まらない欠点があった。そこで合成高分子の中から標準ポリカチオンを見いだす努力が続けられ、桐榮恭二教授(岡山大理)により、塩化ポリジアリルジメチルアンモニウム(PDAC, 商品名Cat-Floc)が優れたポリカチオン標準物質であることが見いだされた3)。これはモノマーである塩化ジメチルジアリルアンモニウムの環化重合により合成される線状ポリマーであるために均一荷電の理想的なポリカチオンであり、pHによる影響を受けない。
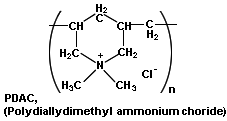
PVSKはポリビニルアルコールの硫酸エステルで、エステル化度から計算により規定度を決めることができるが、最も簡便で正確な方法はゼフィラミンを一次標準として標定する方法である。ゼフィラミンは60℃減圧乾燥して恒量として用いる。桐榮先生らはシリカゲルデシケーター中での一昼夜乾燥で一定組成の一水塩となる塩化セチルピリジニウムが吸湿性でないため使いやすいとしている4)。
【滴定終点の決定法】
カチオン染料であるTBはアニオンコロイドに吸着して青色から赤紫色に鋭敏に変化する。これはメタクロマジーとして昔からよく知られていた現象である。アニオンコロイドの直接滴定にはアニオン色素のカルコンや蛍光色素のANSも用いることができる。カルコンはPDACに吸着されたときの赤から青への色調変化を示し、蛍光色素ANSは吸着により強い蛍光を示す。蛍光検出では10-6モルの低濃度の滴定が可能である。
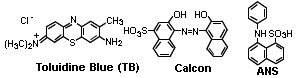
以下に使いやすいコロイド滴定キットの内容を紹介する。
【コロイド滴定キットの内容】
試薬A:PVSK
試薬B:PDAC
試薬C:ゼフィラミン
試薬D:TB水溶液
【キットの使用法】
・試薬A、Bはそれぞれを純水に溶解し、全量を1000mlとすれば、約1/400Nの滴定溶液となる。
・試薬Cは内容量を純水に溶かし、500mlとすれば、正確な1/400Nの一次標準液となる。泡立ちのためにメニスカスを合わせにくいので撹拌には注意する。(f=1.000±0.004に調製済み)
・試薬Dは全量を50mlに希釈し0.1%水溶液として用いる。
【滴定操作法】
カチオンコロイドはTBを指示薬にして、PVSK標準溶液でそのまま滴定できる。天然コロイドイオンの荷電はカルボキシル基、硫酸基、水酸基などに由来するアニオン性が多い。その場合、過剰のPDAC標準溶液を加えアニオンコロイドを沈殿させて後、TBを指示薬に逆滴定する。
【滴定に影響する因子】
再現性のある測定のためには1/400〜1/4000Nの稀薄溶液で滴定する事が望ましい。高濃度の塩類が存在すると、イオン会合反応を妨げるために、終点の検出ができなくなる。食塩は0.1%以下が望ましく、塩化カルシウムは0.005%以下でなければならない。
pHによって、コロイドの表面荷電は変化するので、一定pHで測定する必要がある。逆にいろいろのpH条件で滴定して、滴定値から計算したミリ当量/g値とpHとの関係(コロイド滴定曲線)を求めると、コロイドの表面荷電の変化を求めることができる。硫酸エステルは全pHにおいて、完全解離であり、カルボキシル基はpH11に至って完全に解離することを知ることができる5)。コロイド滴定の最近の進歩については服部による詳しい総説がある6)。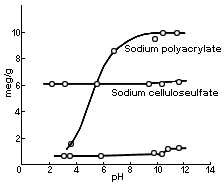
pH profiles of sodium cellulosesulfate, sodium polyacrylate, and agar.3)
参考文献
1)寺山 宏、ぶんせき、1979、623〜628.
2)千手諒一、「コロイド滴定法」(1969), (南江堂).
3)桐榮恭二、河田 清、分析化学、21、1510〜1515 (1972).
4)K.Toei, T.Kohara, Anal. Chim. Acta, 83,59 (1976).
5)K.Ueno, K.Kine, J. Chem. Edu., 62, 627〜629.
6)服部敏明、ドージンニュース No.74,11〜15 (1995).